
★要点
下関市×北九州市の関門エリアが、国際認証団体Green Destinationsの「TOP100 Stories 2025」に初選出。関門橋や関門トンネルを学ぶ“インフラツーリズム”と、行政・事業者・住民が連携するエリアマネジメントが評価された。
★背景
観光は量から質へ。環境・文化・地域貢献を軸に「稼ぐ×守る」を両立する地方の再設計が世界基準になり、点の名所より“面の運営力”が問われる時代に入った。
関門海峡は、渡るだけの場所ではない。橋もトンネルも、学びと誇りの教材だ。関門エリア(山口県下関市/福岡県北九州市)が、世界の持続可能な観光地TOP100に国内で初めて選ばれた。評価されたのは、観光パンフでは拾いきれない“運営の巧さ”。インフラを資源化し、二つの都市が一つの観光圏として機能する成功事例と言える。
“橋とトンネル”を観光資源に——インフラツーリズムの設計。
関門橋や関門トンネルは、地域にとって日常の動脈だ。その当たり前を、学びの体験に翻訳したのが関門エリアの強みである。構造や歴史をガイドと辿り、海峡の地形・物流・産業の関係性を体感する。移動の裏側にある技術・維持管理・地域経済の循環を見える化し、観光の満足を“知る喜び”で高める仕掛けだ。
観光の脱・大量消費は、目玉を増やすことではない。既存資産の再編集にある。交通インフラを“行くだけの通過点”から“学ぶ目的地”に変えることで、滞在時間は延び、回遊は深くなる。地域が積み上げてきた公共投資が、次世代の体験価値に転化する。
二都市一圏のエリアマネジメント——連携こそ最大の観光資源。
今回の選出理由には、行政の枠を越えた連携がある。下関市と北九州市、観光・インフラ事業者、地域団体、住民を束ねるDMO(関門DMO)がハブとなり、広域での企画・情報発信・受入体制を設計。フェリーで5分という地の利を“二都市一圏”の運営で活かした。
持続可能性は、施設単体では達成できない。交通・宿泊・文化資源・商い・環境配慮の接続点に、運営の解像度が問われる。共通チケット、回遊導線のデザイン、ピーク分散、住民参加のプログラム——細部の積み重ねが、来訪者体験と地域受容性を同時に底上げする。
世界基準“TOP100 Stories”の意味——量より質、物語の共有。
Green DestinationsのTOP100は、観光地の“いい話”を選ぶ称号ではない。環境保護、文化継承、地域貢献の具体策とそのエビデンスを審査し、改善の物語(ストーリー)を共有する国際プラットフォームだ。選出は“到達点”ではなく“出発点”。データとプロセスを公開し続け、世界の観光地と学び合うためのパスポートである。
関門エリアの文脈は、海峡を挟む境界性にこそ価値があるという逆転の発想だ。異なる行政・文化・産業をつなぐ実装力が、持続可能性の推進力になる。観光は地域づくりの鏡。連携の成熟度が、そのままブランドの厚みになる。
“過ごす・学ぶ・関わる”を束ねる。
今回の受賞から、他の自治体もいろいろと学ぶ点がある。それは、三つの層を束ねる編集だ。第一に“過ごす”。海峡を眺め、港を歩く日常の贅沢を、長期滞在の過ごし方として磨く。第二に“学ぶ”。インフラツアーを学校・企業研修と接続し、地域の技術史・防災・環境教育に展開する。第三に“関わる”。清掃・保全・ローカルマーケットなど、旅人が担い手になる余白を用意する。
観光は地域のOSだ。関門エリアの挑戦は、名所の足し算ではなく、連携と運営の掛け算で価値を更新し続ける“プロセスの観光”。国内初のTOP100選出は、そのやり方が世界に通じる証左になった。

公式サイト
GREEN DESTINATIONS FOUNDATION
https://greendestinationsjp.org/
2025 Green Destinations Top 100 Stories
関門エリアの受賞内容について(PDF)
https://www.greendestinations.org/wp-content/uploads/2025/09/KANMON-2025Top100-Good-PracticeStory.pdf
あわせて読みたい記事

【新しい観光の在り方】八ヶ岳の森を“学ぶ旅”へ。植物と循環を体感する研究拠点「TENOHA TATESHINA Lab.」の価値を考える。

【9/25はSDGsの日】“観光の未来”を測る物差し──NEWTが選ぶ「サステナブルツーリズム先進自治体TOP30」の読み方。
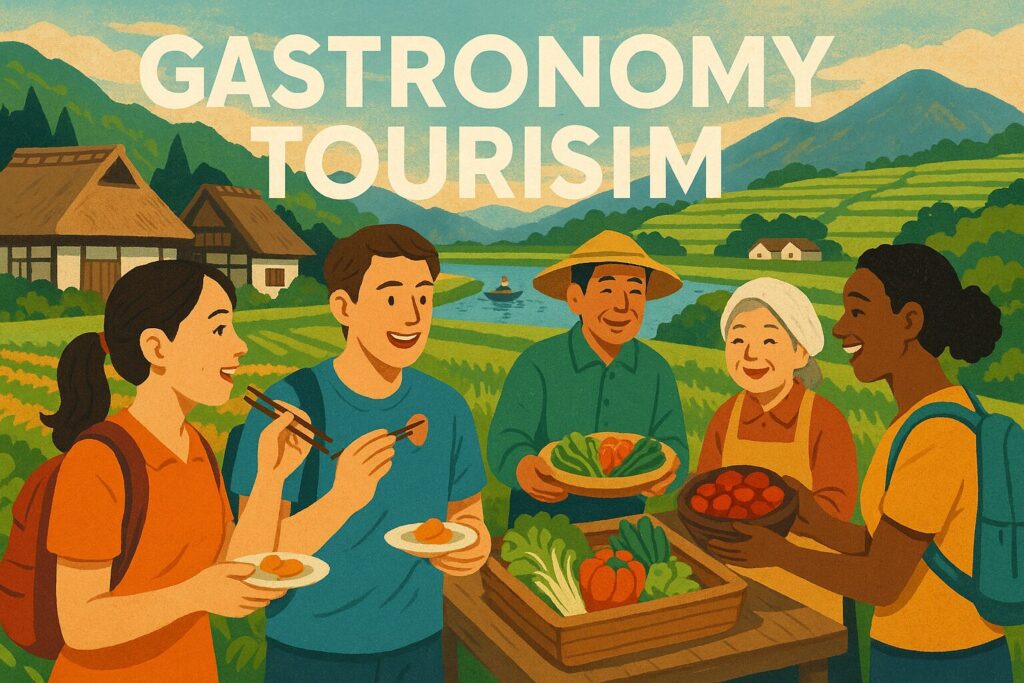
「食」が地方を変える。観光庁が進める「ガストロノミーツーリズム」とは何か?

ラピダスの進出で世界から注目される千歳市と地元観光施設のSDGs推進
