
★要点
フランス酪農業界が最新レポート「Sustainable Dairy Farming」で、1990年比27%の排出削減、草地による大規模な炭素貯蔵、気候変動への適応策をセットで示し、“牛乳がどんな地球環境の上に成り立っているのか”を可視化した。
★背景
人類起源の温室効果ガスの約14〜15%が畜産由来とされる中でオープン知識FAO、酪農を「問題」として切り捨てるのではなく、炭素削減・再エネ・生物多様性・動物福祉を同時に組み立て直すことが、ヨーロッパだけでなく日本の酪農にも突きつけられた課題になっている。
朝のカフェオレ、コンビニのヨーグルト、シチューの牛乳。私たちの日常を支える一杯の向こう側で、酪農は気候危機のど真ん中にいる。畜産由来の温室効果ガスは、人類の排出全体の一割強を占めるとされ、その大部分を牛が担う。
フランスの酪農業界団体CNIELが発表したレポート「Sustainable Dairy Farming」は、その厳しい現実から目を逸らさない。排出削減だけでなく、草地の炭素貯蔵、再エネの活用、猛暑への適応、牛の快適性までを一体で描いた“持続可能な牧場”の設計図だ。気候変動の加速と畜産への批判が強まる世界で、「それでも酪農を続けるなら、ここまでやる」という覚悟のラインが見えてくる。
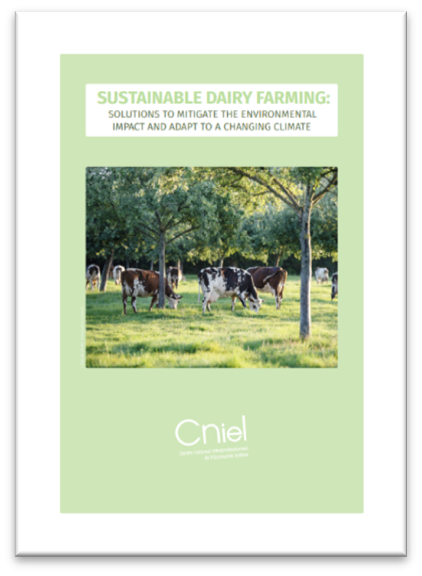
排出27%減。“見える化”された牧場から始まる
フランスの酪農は、1990年から2021年の間に温室効果ガス排出量を27%削減したという。いきなり“魔法の技術”が現れたわけではない。小さな改善を積み重ねるための「物差し」が導入されたことが大きい。
その物差しが、診断ツール「CAP’2ER®」だ。EUプロジェクト「Carbon Dairy」と連携して開発されたこのツールは、牧場ごとに牛の頭数、飼料の種類、草地の面積、エネルギー使用量などを入力し、1リットルの乳を生産するまでに何キロのCO₂が出ているかを可視化する。
数字が見えれば、打ち手も具体化する。発酵飼料の改良でメタン排出を抑える。乳量の高い牛を選びつつ、無理な多産を避ける。自家牧草の比率を増やし、輸入飼料に伴う“隠れた排出”を減らす。こうした一つひとつの改善を、農家任せではなくデータで支える仕組みだ。
気候変動報道では「畜産=悪者」といった単純な図式が語られがちだが、実際には地域ごとの事情も、牧場ごとの工夫も違う。ツールが“平均値”ではなくそれぞれの牧場のストーリーを見せることで、酪農家自身が「どこまで減らせるのか」を自分事として捉えられるようになる。
草地は“隠れた炭素バンク”——耕さないという選択
酪農の環境負荷と聞くと、メタンや糞尿が真っ先に思い浮かぶ。しかしCNIELのレポートが強調するのは、「草地そのものが巨大な炭素貯蔵庫である」という事実だ。フランスの酪農地帯では、放牧地や草地の土壌に平均1ヘクタールあたり約85トンのCO₂換算の炭素が蓄えられているとされる。
深く張った草の根が二酸化炭素を土中に固定し、牧草地が長く維持されればされるほど、そのストックは増えていく。レポートは、土壌中の有機炭素を長期的に観測する「牛・羊畜産土壌における有機炭素観測所(OCBO)」プロジェクトも紹介する。目的はシンプルだ。“牧草地をそのまま保つことが、どれだけの炭素を守ることになるのか”を科学的に示すこと。
逆に言えば、牧草地を耕してトウモロコシ畑や他用途に変えれば、その炭素を一気に大気に放出してしまうリスクがある。ブラジル・アマゾンで、牧場開発のための森林破壊がメタンとCO₂のダブルパンチとなっている構図と、本質的には同じだ。
「牛を減らせばいい」という単純化ではなく、どの土地を草地のまま守るのか、どの牧場が炭素を“貯めている”のかを評価し、報酬に結びつける仕組みがなければ、本当に持続可能な酪農は成り立たない。その点で、草地を“自然由来のインフラ”として位置づけるフランスのアプローチは、脱炭素と生物多様性を同時に見る視点を示している。
暑さに弱い牛と、熱くなり続けるヨーロッパ
酪農の持続可能性は、排出削減だけでは測れない。気候そのものが変われば、牧場の現場が立ちゆかなくなるからだ。
CNIELが支援した「ClimA-Lait」プログラムは、フランス全土20地域で、気候変動が酪農経営に与える影響を分析した。乳牛は寒さには比較的強いが、暑さには弱い。酷暑日が増えれば、乳量は落ち、病気が増え、農家の作業負担も跳ね上がる。
そこで検討されているのは、「風通しを重視した牛舎設計」「日陰を増やす植栽」「耐暑性を持つ血統の研究」といった、きわめて具体的な“気候適応”だ。
牛の快適性(アニマルウェルフェア)は、単なる倫理の問題ではない。暑さでストレスを受けた牛は乳量が落ち、繁殖がうまくいかなくなり、経営そのものが成り立たなくなる。動物福祉と経済性、気候変動対策が一本の線でつながる。
気候危機下の酪農は、「どれだけ排出を減らすか」と同時に、「変わりゆく気候の中で、牛と人がどう生き延びるか」というサバイバルの問いに応える産業でもある。
「肉=悪」では議論が進まない。メディアが扱うべき“グレーゾーン”
世界の温室効果ガス排出の約3分の1が農食システム由来、そのうち大半を肉と乳製品が占めるという分析もある。にもかかわらず、主要メディアの気候報道で畜産が正面から取り上げられる割合はごくわずかだという調査結果も出ている。
理由は単純だ。肉と乳製品は、多くの人にとって「日常」であり、「文化」だからだ。減らそうと言えば反発も大きい。政治もメディアも、タブーに触れることを避けがちになる。
そこでCNIELのレポートが取る戦略は、「やめるか続けるか」の二択ではなく、「続けるならどう変えるか」を数字で示すことだ。既に27%は減らせた。草地は大量の炭素を抱え込んでいる。気候適応と動物福祉を両立させる研究が進んでいる。こうした“グレーゾーン”の努力を見える形にしない限り、「肉・乳は今すぐやめるべきだ」という極論と、「問題などない」という否定論の間で議論は空回りし続ける。
フランスの取り組みは、「批判を浴びている産業だからこそ、科学とデータで変わろうとする」という姿勢を示している。その姿勢をどう評価し、どう議論につなげるかは、消費者とメディア、そして政策側に委ねられている。
日本の酪農への示唆、“炭素も風景も守る”という約束
日本でも、酪農は岐路に立っている。原料乳価格の高騰、飼料高、担い手不足。そこに「気候変動」という重いテーマが重なる。一方で、那須千本松牧場のように、放牧地の維持や堆肥循環を通じて、地域の風景と環境負荷低減を両立させようとする動きも生まれている。CNIELのレポートは、こうした国内の挑戦を後押しする“参照枠”になりうる。
日本の酪農が学べるポイントは多い。「牧場ごとの排出量を見える化する診断ツールの導入」、「草地の炭素貯蔵量を評価し、維持するほど価値が出る仕組み」、「猛暑・豪雨に備えた牛舎設計と、地域単位の気候リスク評価」。そして何より、「牛乳の“安さ”だけで価値を測らない」という社会の合意だ。価格競争だけを続ければ、最初に削られるのは環境への投資と、牛と人の余白である。
牛乳を手に取るとき、「この一杯は、どんな草地とどんな牧場から来たのか」。そんな問いを消費者が持つことができれば、酪農は“問題児”ではなく、“地域の炭素循環を担う仕事”として再定義されるだろう。
『Sustainable Daily Farming』
レポートPDFダウンロードはこちら:
(英語)Sustainable Daily Farming
(フランス語)L’ELEVAGE LAITIER DURABLE
あわせて読みたい記事

木くず、おがくず、牛糞、鶏糞。土づくりと農業と地域内循環。

【明治×北海道大学×ファームノート】子牛の健康づくりから始める持続可能な酪農業

持続可能な循環型酪農を実践する那須千本松牧場 夏休みフェスティバル開催
