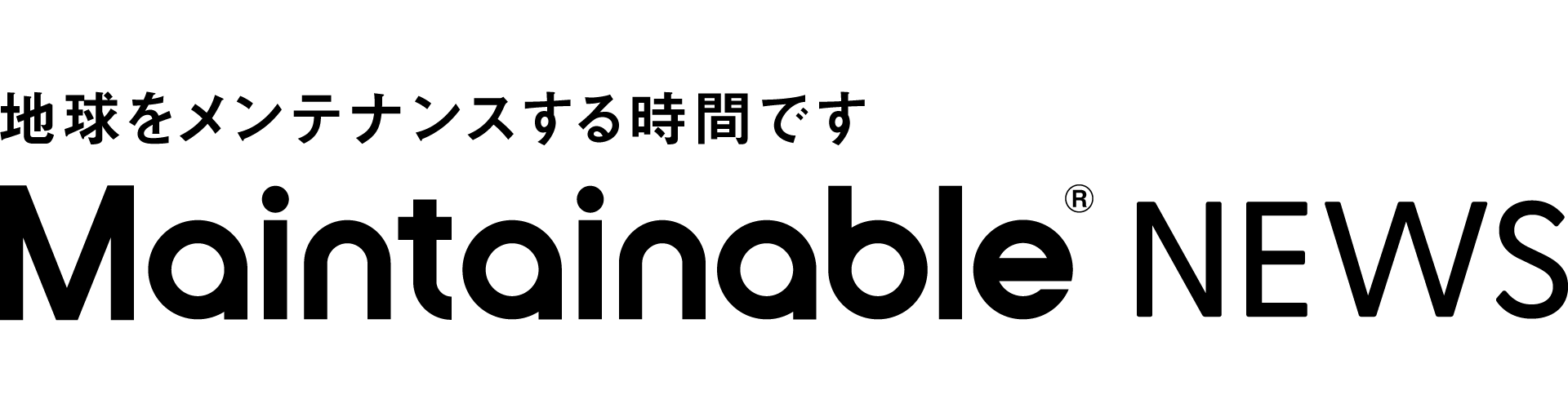★要点
横浜市が約1,200拠点の廃棄物管理をデジタル化し、「pool」による計量・データ連携で回収ルートを高度化。“ごみゼロルート回収”を掲げ、コスト削減とCO₂削減、資源循環の見える化を同時にねらう都市型モデルだ。
★背景
気候危機と人手不足、財政制約が重なる中、自治体インフラのDXは待ったなし。焼却中心の日本型廃棄物処理から、データを起点に「出さない・回す」仕組みへ――都市の“静脈”を更新する転換点にある。
燃えるごみ、資源ごみ、事業系ごみ――都市の日常を支えるトラックの走行ルートは、長く経験と勘に頼ってきた。そこに「ごみゼロルート回収」という、少し挑発的な言葉を掲げて割り込もうとしているのが、横浜市とレコテックだ。
2025年12月、区役所や学校など約200拠点で試験運用を開始。2026年4月には、約1,200拠点すべてをつなぐデジタル基盤へと広げる計画である。廃棄物管理という“見えないインフラ”の設計図を書き換え、サーキュラーシティへの土台をつくる試みだ。
1,200拠点を束ねるデータの筋道。「pool」が描く新しい回収ロジック
今回の舞台は、日本最大の政令指定都市・横浜市だ。対象は市役所関連施設約1,200拠点。区役所、学校、地区センターなど、日々ごみと資源が排出される場所を、一つのプラットフォームで束ねようとしている。
その要となるのが、レコテックの次世代型計量管理システム「pool」である。排出される廃棄物・資源の量や種類を細かく記録し、リアルタイムで可視化。排出者、回収事業者、行政のあいだでデータを共有し、回収頻度やルートを動的に最適化していく。
試験運用の第一段階として、2025年12月15日から約200拠点で実装が始まる。ここで検証されるのは三つだ。
ひとつは「見える化」。どこで、何が、どれだけ捨てられているのか。量と中身を時系列で追えるようになれば、漫然とした「ごみの多い部署」から、具体的な「減らせる行動」へと議論を進められる。
二つ目は「回収オペレーション」。回収車は、満杯に近いコンテナを優先し、空に近い場所は飛ばすといった運行が可能になる。ごみが出ていない場所にトラックが走る“空振り回収”を減らすことで、燃料・人件費・CO₂排出をまとめて削る狙いだ。
三つ目は「職員の手間」。帳票や電話、メールでバラバラに管理されていた排出・回収データが一元化されれば、確認や突合せに費やしていた時間を減らせる。横浜市の担当者にとっても、現場の回収事業者にとっても、“紙からデータへ”の一歩は小さくない。
2026年4月、これらの検証結果を踏まえ、全1,200拠点への拡大をめざすという。成功すれば、「都市規模でのごみゼロルート回収」というコンセプトが現実の交通網に落ちてくる。

ごみは“終点”ではなく“起点”。サーキュラーエコノミーの土台づくり
ごみ収集車が向かう先は、焼却炉か最終処分場。そこを都市の「終点」と見なしてきたのが、従来の発想だった。だがサーキュラーエコノミーの視点で見れば、廃棄物管理は「資源の循環経路をデザインする入口」である。
レコテックは「pool」を単なる計量システムにはとどめていない。排出側向けの計量管理、調達側向けのPCR(再生プラスチック)材調達プラットフォーム、そして国産100%PCR材「pool resin」へと機能を拡張し、資源循環の川上と川下をつなぐ仕組みを組み上げつつある。
横浜市での取り組みは、その基盤としての意味が大きい。1,200拠点からの排出データが蓄積されれば、どの部門でどの素材が多く廃棄されているか、どの季節に廃棄量が跳ね上がるか、といった傾向が見えてくる。
それは、調達仕様の見直しや、リユース・リサイクル施策の設計に直結する情報だ。
たとえば、オフィス家具、文具、什器といった品目ごとの寿命や廃棄量が分かれば、「長く使える設計」や「分解しやすい素材」への切り替えをメーカーに求めやすくなる。自治体が大口ユーザーとして動けば、サプライチェーン側の意識も変わる。
都市のサーキュラーエコノミーは、派手な新素材だけで回るわけではない。日々排出されるごみの粒度を上げて把握し、調達と設計にフィードバックする――その地味なループを回せるかどうかが、持続可能性の実力を分ける。
現場DXの正念場、トラックとごみ箱のあいだにある“人の仕事”
華やかなコンセプトの裏側には、現場の負荷という現実がある。廃棄物管理DXも例外ではない。
今回のモデルでは、各拠点の排出状況を「pool」で一括管理し、収集運搬の事業者とリアルタイムで連携する。システム上はスムーズに見えるが、実際にはごみ箱に貼られたQRコードを読み取る人がいて、コンテナの入れ替えをする人がいて、トラックを運転する人がいる。
日本中で進むトラックドライバー不足、深夜・早朝勤務の敬遠、燃料価格の高騰――そうした構造的な課題を、デジタル化だけで一気に解消することはできない。むしろDXの成否は、「どこまで現場の動きに合わせて設計できるか」にかかっている。
横浜市の試験運用は、その意味で“現場とシステムのすり合わせ期間”でもある。
・収集ルートの変更が頻繁すぎて、ドライバーが混乱しないか
・ごみ箱側の入力操作が煩雑になり、結局データが抜け落ちないか
・廃棄物の区分ルールとデータの分類体系が噛み合っているか
こうした問いに一つずつ答えながら、自治体・事業者・システムベンダーの役割分担を再編集していく必要がある。DXとは、既存の業務フローにシステムを“貼り付ける”ことではない。業務そのものを、データがまわりやすい形へ作り替えるプロセスでもあるからだ。
横浜モデルからアジアの静脈インフラへ。“ごみゼロルート”の輸出可能性
レコテック代表の野崎さんは、今回のプロジェクトについて「日本最大の政令指定都市である横浜市の重要なインフラである廃棄物処理、そして今後ますます重要な資源循環プラットフォーム構築の一翼を担いたい」と述べている。さらに、その先に「都市化が進むアジア全体の持続可能な静脈インフラのモデル構築」を見据えると語る。
人口密度が高く、廃棄物の焼却依存度も高い東アジアの大都市にとって、「ごみゼロルート回収」は共通課題の解法になりうる。
・どの拠点から、どの種類の廃棄物が、どれだけ出ているか
・そのうち、どれだけをリユース・リサイクルできているか
・回収のために、どれだけの燃料・人件費・CO₂がかかっているか
これらを一つのプラットフォームで可視化し、改善のPDCAを回す。やっていることは地味だが、その積み重ねが都市のカーボンフットプリントを確実に削っていく。
すでに、駅空間を「循環ハブ」と見立て、剪定枝などの植物性廃棄物を地域資源として循環させようとするJR東日本の取り組みも動き始めている。公共インフラを起点に、資源の流れを組み替えようとする動きは、鉄道会社にも自治体にも共通している。
横浜モデルが2026年以降どこまで精緻化され、他都市へ展開されるのか。問われるのは、単発の実証実験ではなく、「運用し続けられるルール」としての設計力だ。
廃棄物管理は、市民から見えにくい裏方の仕事である。その裏方を、データと共創でアップデートできるかどうか。ごみ収集車のルートから始まる都市の変革は、着実に進行しているようだ。
あわせて読みたい記事

【駅が「循環ハブ」に進化する】JR東日本とSpacewaspが仕掛ける、植物性廃棄物アップサイクルの未来