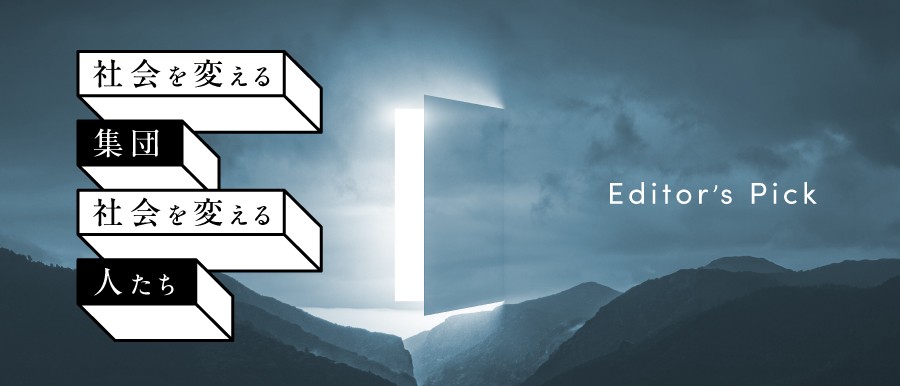
【後編】
理工系分野での女性の活躍を応援する企業
※2024年8月23日、アンリツ本社で開催された「リコチャレ2024 見えないものを“はかる”!」会場でのスピーチ「ものづくりの魔法~理系で夢をカタチに」より構成。

アンリツ株式会社 理事 CTO 先端技術研究所長 野田華子さん
1992年アンリツ入社。技術本部技術企画部長、技術本部先進技術開発センター長を経て、2019年より理事CTO技術本部長、20年より現職。
アンリツ先端技術研究所長の野田華子さんは、自身のキャリアとアンリツの取り組みを語る中で、「理工系学生の可能性を広げる社会の大切さ」を強調する。
野田さんは、女性向けのSTEAM教育(科学、技術、工学、芸術、数学を融合した教育)の推進に力を注いでおり、スピーチの中でも自ら設計したCAD作品を例に挙げ「創造力と技術を掛け合わせて新しいものを生み出す楽しさを皆さんにお伝えしたい」と、会場に集まった学生たちに語りかけた。
「私たちアンリツという会社が目指すのは、理工系分野を単なる職業の選択肢としてではなく、技術開発に関わる仕事を“生涯を通じて続けられる情熱”として感じてもらうことです」。
「はかる」を超える価値、新領域開拓の先端で
「私たちが取り組むのは、“見えないものを見える化する”技術です。通信計測だけでなく、EV(電気自動車)のバッテリー性能評価や医薬品の品質検査など、幅広い領域での応用が求められています。」
アンリツの主な事業セグメントは「通信計測」「PQA(Products Quality Assurance)」「環境計測」で、6G、データセンター、光電融合デバイス、医薬品用品質検査技術まで、研究開発テーマは実に多岐に渡っている。
アンリツの先端技術研究所は「はかる」技術でこれからの社会を支え続けるため、高度な計測技術の開発と適用領域の拡大を目指し、研究開発とリサーチを行う機関だ。
その所長である野田さんは現在、6Gに向けた研究と超高感度センサを実現するためのグラフェンの研究を指揮している。6G研究では、Full-Duplex通信の研究において、AI技術を使い、同じ周波数帯で届く電波の分離に成功した。これにより各通信端末からの電波信号の届き具合が可視化できる。グラフェン研究では、ナノメートル単位の微細な加工技術を確立し、グラフェンの物性を評価するための技術を取得するという成果を上げた。
またプライベートでも野田さんは陶芸、金継ぎ、3Dプリントなどに親しんできた。学生たちに将来への想いを語りかける背景には、自身が歩んできたそれらの多様なものづくりの経験があるのだ。
「リコチャレ2024」は、内閣府男女共同参画局が中心となって行っている。女子中高生や女子学生の方たちが理工系分野に興味・関心を持って、将来の自分をしっかりイメージして進路選択にチャレンジすることを応援している。
女性がさまざまな分野にチャレンジしていくことで、多様な視点や発想が社会に加わるのは自明の理だ。そしてダイバーシティ(多様性)とインクルージョン(包摂)によってこそ、これからの活力ある生き生きとした社会は実現される。
アンリツはこの趣旨に共鳴し、技術が社会にどのように役立っているのかを感じてもらい、進路を決める前の学生たちに、理工系を選択肢に入れてもらえるよう「リコチャレ2024 見えないものを“はかる”!」を企画した。

野田さんの熱いメッセージに、真剣に耳を傾ける学生たち。
理工系教育と文系能力の融合――未来の人材像とは
AI(人工知能)の活用もアンリツの重要なテーマの一つだ。野田さんは、AIを使いこなすスキルの重要性を強調し、「これからの時代は、AIに使われるのではなく、AIを使い倒す人材が求められます」と語った。例えば、データ解析やパターン認識の分野でAIを活用することによって、新たな測定技術や診断技術が生まれている。
「ゼロから1を生み出す力を持つ人材が、これからのアンリツを支える柱となります。そのためには、個々の好奇心や探究心を引き出し、創造的な課題解決能力を育む環境が不可欠です」。
新しい課題に対応する技術を自ら生み出していくことの重要性を野田さんは力説する。そこから「はかる」という概念を超えた、次の時代を形作る基盤が創造されていくことを自身もよく知っているからだ。
野田さんはまた、理工系教育と文系能力の融合がとても重要だと話しかけた。
「皆さんは知っているでしょうか? 実は技術開発の世界では、単に技術を扱う理工系的なスキルだけでなく、問題を言語化して相手に伝えるコミュニケーション能力も必要とされます。つまり理工系と文系の境界線は実はもっと融合されるべきで、どちらの視点も持った人材が求められているのです。
洞察力や共鳴力を持って、多様な背景を持った人たちとコミュニケーションをとり、協働できる力が、これからの技術者にはますます不可欠です」と語った。
「データの相関性を見抜く能力や、異なる視点を統合して新しい価値を創出する能力。技術の進化は、ひとりひとりの好奇心や探究心から生まれます。
だからもしあなたたちが壁に直面したとしても、それを乗り越えようとする挑戦心があれば、きっと未来は切り開かれます」。
時代の突端で計測技術を強い武器に、次の社会価値を創造しようと前進する企業アンリツと、その先端技術研究所所長である野田さんの存在は、会場に集まった学生たちにとって、きっと将来の大きな目標に見えたことだろう。
2024年8月23日「リコチャレ2024 見えないものを“はかる” !」会場の様子から




集まった学生たちは、アンリツ本社グローバル棟1Fフロアに設置されている「アンリツギャラリー」で創業以来130年のアンリツの多様な歴史を学んだ後、理工系の先輩でもある女性研究員たちのナビゲートで、5Gラボへ。ここで無線通信の電波計測ソリューションを使った実験をはじめ、さまざまな見えないものを「はかる」技術のおもしろさと先端技術の凄さを思い思いに体験した。「体験型が充実していて楽しかった」「今後、文理を選ぶ上で参考にさせていただきます」「電話の歴史についてもっと知りたかった」などの声が続出した。
技術者の天国とは
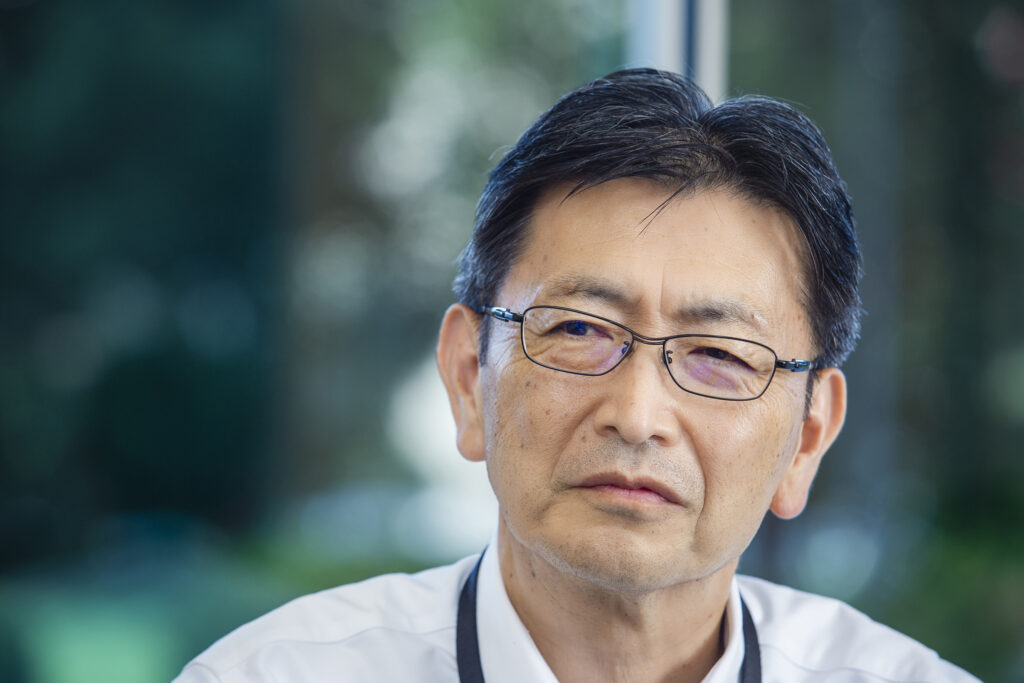
アンリツ株式会社 執行役員 人事総務統括 人事総務部長 A-SKILLsセンター長 坂本貴司さん
1985年電気通信大学電気通信学部卒、安立電気入社(1985年10月、アンリツに社名変更)。計測事業本部マーケティング本部商品企画部長、計測事業統括部長等を経て、20年より現職。
日本の計測技術の歴史を作ってきたアンリツは、技術革新を続ける同社を愛し、集う社員たちから「技術者の天国」という呼び方もされてきた。この恵まれた歴史は、同社代表の濱田社長の言葉の端々からも感じられたことだ。
同社の執行役員で人事総務統括 人事総務部長であり、「A-SKILLs/Anritsu Skills Training Center」センター長も務める坂本貴司さんは、アンリツが絶え間ない技術研究と開発の歴史の中で常に革新を続けられる理由の一つには、技術者たちが自由に創造し、挑戦できる環境があると語る。
「技術者が自らの限界を超え、新しい領域に挑むことができる。それがアンリツの企業文化です」
同社では、エンジニアが「はかる」という分野を基盤に、新しい価値を創造することが常に奨励されている。
例えば、通信計測における先進技術の開発では、次世代通信規格である6Gの研究にいち早く着手。その背景にあるのは「オリジナル&ハイレベル」という同社ならではの理念だ。
この理念は単なるスローガンにとどまらず、技術者たちが自らの創造性を最大限に発揮するためのガイドラインとしても機能しているようだ。
「単に現状を維持するのではなく、常に革新を追求する。それがアンリツのDNAであり、私たちの誇りなのです」。
アンリツでは、プロジェクトごとに柔軟なチームを編成し、技術者が自分の得意分野や興味を最大限に活かせるよう配慮するなど、「挑戦の文化」を享受できる環境を整えている。
「技術者たちがやりたいことを自由に追求できる。それがアンリツを技術者の天国たらしめているとも言えますね」と坂本さんは笑顔で語る。
地域共生型の企業活動――多様性推進と環境への配慮
いっぽうアンリツは単なるグローバル企業としての成長だけではなく、地域社会との共生も重要な使命としている。神奈川県厚木市に本社を構える同社は、地域経済の中核として地元とともに歩む姿勢を貫いている。たとえば、障がい者雇用を促進するハピスマという事業体の取り組みもその一つ。
「働く意欲があるのに職場環境が整わないために活躍できない障がい者の方たちに、安定した就労機会を提供するために、株式会社ハピスマを設立しました」と坂本さんは話す。
同社設立以来のモットーは、「決めつけない」「あせらない」「あきらめない」。社名であるハピスマの由来であるHappy & Smileな社風で、障がい者の方たちが生き生きと働ける環境の職場を作り、多様なメンバーによる会社経営を実践している。
多様性の推進においては、女性活躍推進や性的マイノリティ(いわゆるLGBTQの方々)への配慮にも積極的だ。
またアンリツは、環境保全にも積極的だ。同社ではグループ全体でオフィス内でのペットボトル廃止を推進し、自動販売機の商品をすべて缶や紙パックに切り替えた。この取り組みにより、年間のプラスチック廃棄量を大幅に削減。太陽光自家発電・自家消費も推進している。
「こうした行動ひとつひとつが地域全体に広がり、持続可能な未来の礎となることを目指しています」。
厚木市をはじめとする拠点地域での雇用創出や人材育成、社会貢献活動を通じた地域社会発展への寄与を目指すアンリツ。同社が地域社会と深く結びついている点は、単なるビジネス活動を超え、地域全体を支える精神的支柱としての企業の在り方と重要性も示唆しているのではないだろうか。

2021年9月にアンリツ株式会社100%出資のアンリツグループ会社として設立された、株式会社ハピスマ。2021年12月に神奈川県から「化粧品製造業(工場)」としての許可を取得し、2022年1月に障害者雇用促進法に基づき特例子会社の認定を取得した。贈答用石鹸の受託生産を中心に、石鹸製造を主な事業として活動している。
技術者が世界をひとつずつ変えていく
アンリツが目指す未来には、多様性推進と人材育成が欠かせない。現在、同社の女性社員比率は約2割だが、エンジニア職における割合はさらに低い。この現状を打破するために、アンリツは採用、昇進、企業風土などあらゆるレベルでの変革を進めている。
「女性の活躍が制限される社会的なバイアスを取り除き、多様性を推進することが新しい価値を生む鍵だと考えています」と坂本さんは語る。
この言葉を裏付けるように同社では、性別や国籍に関わらず、さまざまなバックグラウンドを持つ人々が集うことで、新しいアイデアや革新を促進しようとしている。
特に注目すべきは、アンリツの海外拠点での事例だ。フィリピンでは女性エンジニアが多数を占め、現地の技術開発をリードしているという。
「女性エンジニアが能力を存分に発揮できる環境を整えることが、私たちの使命の一つです」と坂本さんは力強く述べる。
「『「はかる」を超える。限界を超える。共に持続可能な未来へ。』この経営ビジョンには、実にさまざまな私たちの願いと、これからの社会を変えていきたいという強い意志が現れていると思います。
私たちの目標は、単に新しい市場に進出することではなく、社会が抱える課題を解決することです。それが技術者としての使命であり、アンリツの存在意義だと考えています」。
一般市民の手に届く商品やサービスを提供している企業の名や姿は記憶に残りやすいが、アンリツのような新技術開発の裏方を務める企業の姿は、なかなか一般人の目には映らない。まして見えないものを「はかる」という、極めて高度で困難な計測技術に挑み続ける企業なのだ。専門的知識がなければビジネスの世界でもアンリツのような企業の真の姿を知る者は少ないだろう。
けれど新しいテクノロジーが社会を革新する時、あるいはテクノロジーの変化とともに新しい価値や仕組みによって社会全体が変化する時、それを可能にしているのはアンリツのような企業の存在なのだ。
脱炭素、地球環境と生物多様性の保全、気候変動、自然災害、人間行動や暮らしの変化。問題と課題は次々に現れ続ける。そんな時代の数歩先を読み、新たな技術の創出を飽くなき研究精神と高度な計測技術によってサポートし続ける。そんな技術者たちの挑戦スピリッツを信じたい。

聞き手・内野一郎(Maintainable®NEWS編集長)
撮影・高木陽春
【前編】『「はかる」を超える。限界を超える。共に持続可能な未来へ。』技術者たちの思いの本質
➡こちら
シリーズ「社会を変える集団 社会を変える人たち」
持続・循環・再生・保守可能な社会とライフスタイルデザインに取り組むさまざまな企業や研究所、大学などの話題を領域横断でご紹介しているMaintainable®NEWS。新しい取材インタビュー企画として、持続・循環・再生・保守可能な共生社会を実現するために、科学・技術・哲学・クリエーションなどさまざまな領域で実践に取り組む、有為の集団とプレーヤーを独自の視点でフォーカスし、「社会を変える集団 社会を変える人たち」と題して紹介させていただきます。どうぞお楽しみください。
