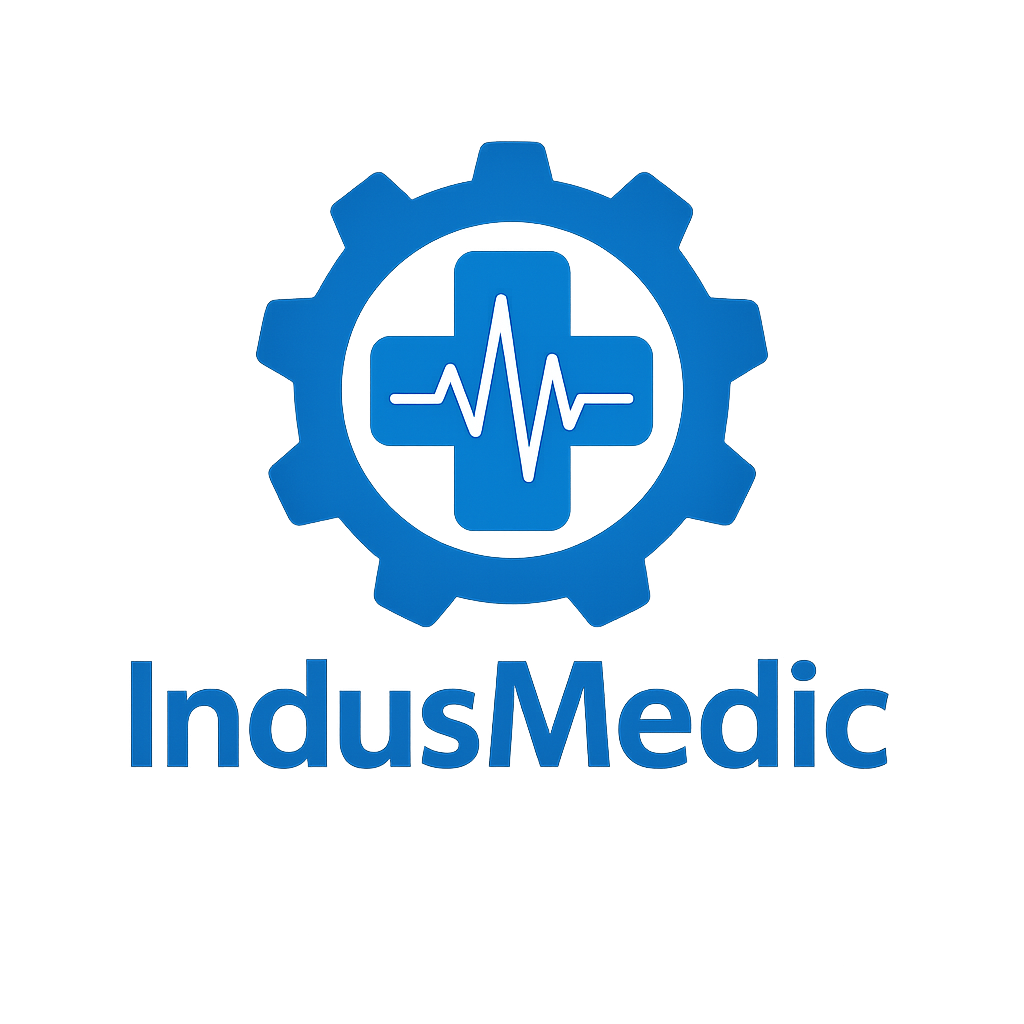
★要点
株式会社SERTが産業機械の修理・保守をワンストップで担う新ブランド「インダスメディック」を立ち上げ。メーカー保証外や海外機も含め、部品調達から現地復旧まで“工場の主治医”として対応し、生産停止のリスクとコストを同時に下げる。
★背景
半導体不足と人手不足、旧型設備の延命需要、サプライチェーンの分断——「壊れたら買い替え」が効かない時代。稼働時間の最大化と装置寿命の延伸は、収益とサステナビリティの両方に直結する経営課題になった。
工場の“痛み”は突然来る。ラインが止まり、納期がずれ、信用が削れる。新調しようにも、納期は数カ月先——そんな現場の現実に割り込むのが、産業機械の救急外来「インダスメディック」だ。メーカーをまたぎ、古い機械も海外製も診る。直す、動かす、延ばす。ものづくりの足腰を、修理という現実解で支える。
診断から退院まで——“機械のドクター”の動線。
ブランド名が示す通り、狙いは医療の比喩にある。受付(窓口)は国内、症状の問診に続き、分解・測定・交換・配線・調整までを一気通貫。必要部材は自社在庫とアジア圏の調達網で確保し、現場復旧の時間を削る。対象は半導体製造装置やFAシステム、検査機、分析機器、医療機器まで幅広い。メーカー保証外、サービス終了機、対応を断られた案件でも、代替部品と回路リワークで延命策を組む。
なぜ今、修理が“攻め”になるのか?
更新すれば済む話ではなくなった。設備のリードタイムは長期化し、円安が調達コストを押し上げる。熟練保全人材は薄く、突発停止が収益を直撃。さらに、装置の延命は環境負荷の低減にも効く。買い替えに伴う製造・物流由来の排出(エンボディードカーボン)を抑え、資産の使用期間を引き延ばすことは、Scope3対策の一丁目一番地だ。修理は守りではない。稼働率・キャッシュフロー・ESGを同時に押し上げる攻めの施策になった。
“保証の空白地帯”を埋める設計——メーカー横断・国内窓口・海外調達
ポイントは三つ。第一にメーカー横断。ブランドや年代の壁を越えて症状ベースで解決する。第二に国内窓口。海外機でもやり取りは日本語で、意思決定の速度が落ちない。第三に調達網。中国・アジアの製造ネットワークと自社設計で代替部品を設計・製作し、短納期とコストを両立する。メーカー純正の完璧さはないとしても、“今止めない”価値に最適化された仕組みだ。
延命はサーキュラー——部品再生と予兆保全のセット運用へ。
延命は“その場しのぎ”ではない。回路基板の再実装、軸受やシールのオーバーホール、センサーの代替設計。交換した部材の寿命データを記録し、次回の計画停止に織り込む。SERTは今後、IoTセンサーとAI診断を組み合わせた予兆保全にも踏み込むという。突発停止を計画停止に変換できれば、保全はコストではなく投資に変わる。再生・再利用の実績は、調達・設計現場の“次の機種”の仕様にも跳ね返る。
それでも残る論点——責任分界点と安全規格。
第三者修理には、常に二つの壁がある。ひとつは責任分界。メーカー保証との関係、改造の有無、再発時の賠償線引き。もうひとつは安全規格だ。医療機器や高電圧機器では、修理後の適合性評価が必須になる。ここを曖昧にしないために、作業範囲・交換部材・試験結果を台帳化し、顧客と共有するプロトコルが要る。スピードと記録の両立が、現場の信頼を左右する。
次の一手——“工場のカルテ”を共通言語に。
解像度を上げるなら、カルテ化だ。装置ごとにシリアル・構成・保全履歴・異常ログ・使用条件を時系列で蓄積し、QRで現場に紐づける。KPIは「MTBF(平均故障間隔)」「平均復旧時間」「交換部材の再生率」。保全の結果を経営指標に昇華できれば、修理は単なる費用項目ではなく、競争力の源泉になる。インダスメディックが担うべきは、直すことと同じくらい、記録して共有することだ。
あわせて読みたい記事

JR東日本グループ、新幹線の未来を支える「スマートメンテナンス」を本格始動。

修理しながら使う、骨組みまで天然竹の「MUUZ傘」がイケてる話。

【家庭内メンテナンスDXの現在地】エコバックスが提案する次世代の掃除体験「DEEBOT X11 OmniCyclone」。
