観光庁は、地域の食文化を軸にインバウンドの地方誘客を図る「ガストロノミーツーリズム推進事業」を現在、公募中だ。農業・漁業・飲食・宿泊など多様な事業者と連携し、地域独自の食を起点に経済波及効果を最大化するこの取り組み。持続可能な観光の実現と地域活性化を同時に狙う国家事業が、食と観光の関係に新たな価値軸を提示しようとしている。
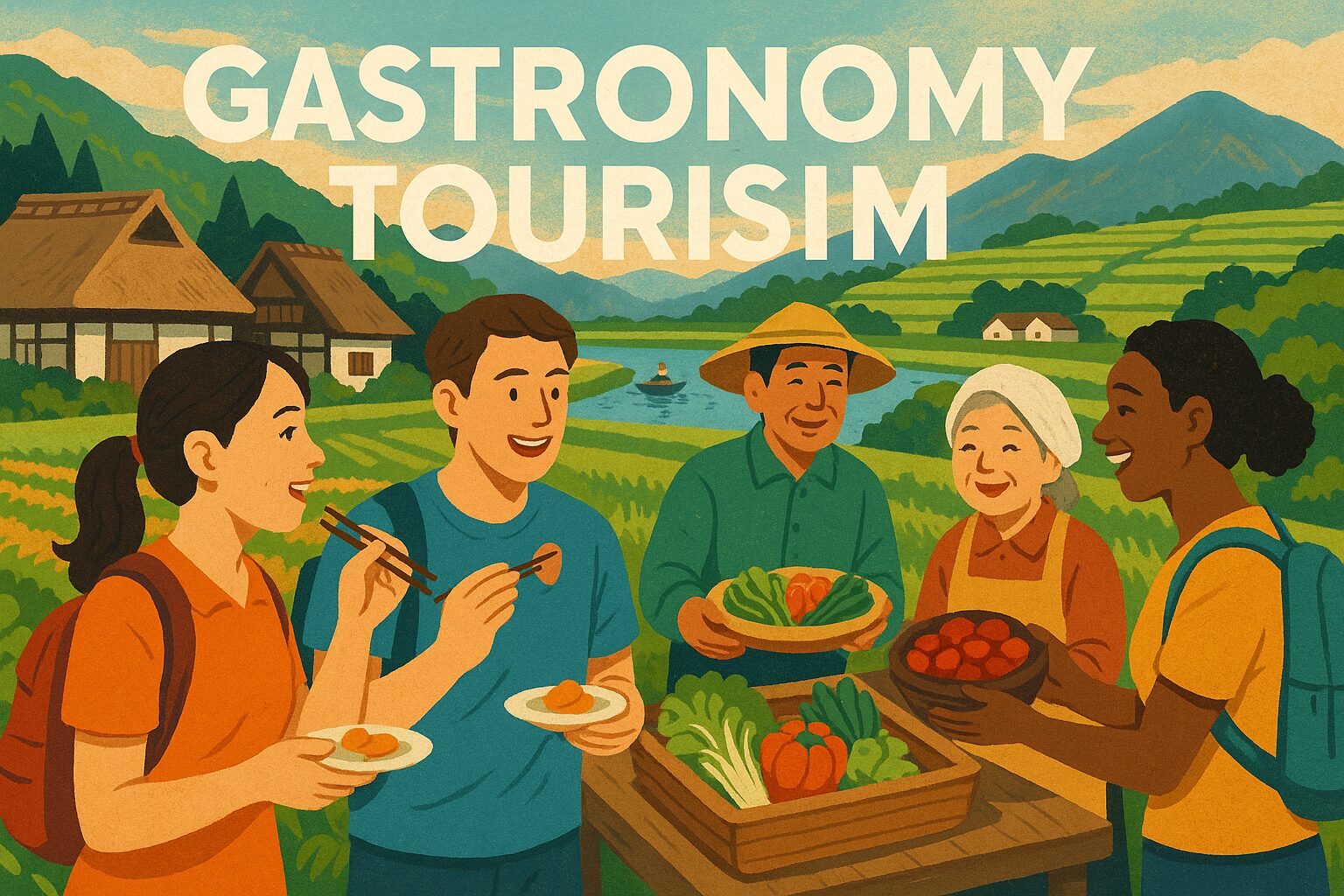
地域の“食の物語”を価値に変える。
多業種連携で魅力を創出し、経済と文化の再生を図る。
「旅の目的が“食”になる」。観光庁が進める「ガストロノミーツーリズム推進事業」は、地域に根ざした食材・習慣・伝統・歴史といった資源を「食文化」として観光体験に昇華させ、国内外の旅行者を惹きつけようとするもの。
本事業の狙いは明確だ。第一に、訪日外国人からの関心が高い「日本の食」の魅力を地方誘客の原動力とし、宿泊・飲食・交通などの観光関連産業を面的に活性化すること。第二に、食資源を中心に、地域の自然環境や文化といった多様なストーリーを紡ぎ、「食を通じた地域のブランド価値創出」を行うことにある。
公募対象となるのは、地方公共団体や観光地域づくり法人(DMO)、飲食・宿泊・農林水産業・交通業などが参画する3者以上の連携体制を持つ団体で、食文化を核にした観光コンテンツの造成・磨き上げに取り組むことが求められる。補助上限は1件あたり2,000万円で、事業には必要に応じて食の専門家による伴走支援も行われる。
重要なのは、単なるイベントや無料モニターツアー、広報物作成にとどまらず、「継続性」と「他地域への展開可能性」が見込まれるスキームの構築。専門家による審査では、地域の独自性やストーリー性、インバウンド対応、経済効果、将来性などが問われる。
この事業が対象とする「ガストロノミーツーリズム」とは、単なる“食べ歩き”とは異なる。気候や風土が育んだ食材とそれをめぐる文化や歴史を学び、五感で楽しむ体験型観光である。観光庁は、世界観光機関(UNWTO)のガイドラインを踏まえ、持続可能な観光、食のブランド化、バリューチェーンの強化、地域主導のマーケティングといった視点も重視している。
現在、日本国内では「地域資源と結びついた本質的なガストロノミーツーリズムの実践例」はまだ少ない。観光庁の取り組みは、そうした現状を打破し、地域が主導する持続可能な観光のロールモデルを育成することにある。事業の公募締切は5月14日。公募要領および問い合わせ先は観光庁公式サイトに掲載されている。
