政府は2025年2月25日、「脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律」および「資源の有効な利用の促進に関する法律」の改正案を閣議決定した。2050年カーボンニュートラルの実現に向け、カーボンプライシング制度の法定化や再生資源の利用義務化、さらにはGX(グリーントランスフォーメーション)分野への財政支援制度など、産業界と自治体の構造転換を促す法整備が大きく前進した。
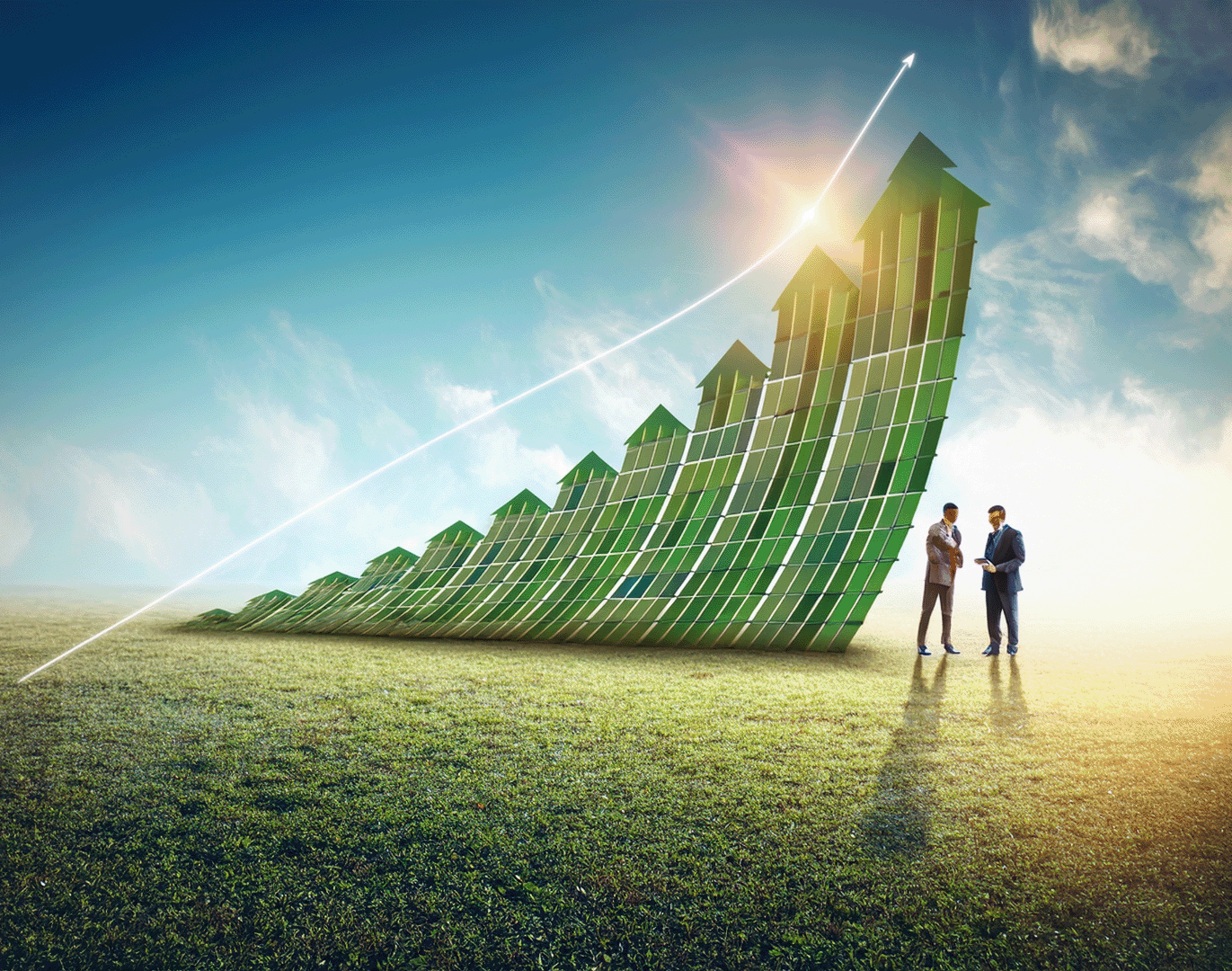
排出量取引と再生資源利用を「義務」に。脱炭素時代の経済運営に問われる対応力。
気候変動と資源制約が重くのしかかるなか、今後の企業経営と自治体運営にとって無視できない法改正が実現した。「脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律」および「資源の有効な利用の促進に関する法律」の改正案が、2025年2月25日、経済産業省と環境省より同時発表された。
この改正案は、2050年のカーボンニュートラル実現に向けて、単なる排出削減を超えた成長戦略としてのグリーントランスフォーメーション(GX)を位置づけたものであり、企業と地域の経済構造そのものに変革を迫る内容となっている。
中心となるのは「排出量取引制度」の法定化だ。2026年度から、CO₂排出量が一定規模を超える事業者に対して、排出枠の取得と報告が義務化される。政府は業種別のガイドラインを策定し、排出枠の無償割当を実施したうえで、市場での売買を可能とする。市場には価格の上下限が設けられ、取引の透明性と安定性が担保される見込みである。
さらに2028年度からは、化石燃料への「賦課金」制度も本格稼働。支払期限や滞納処分といった執行措置に関する規定が整備され、実効性の高い制度として実施される。これらの制度によって得られる財源は、GX投資への支援や、脱炭素関連物資の国内生産促進税制の減収補填に充てられる。
GX実現へ踏み出す新制度。カーボンプライシングと再資源化義務が企業活動を変える。
一方、「資源の有効な利用の促進に関する法律」の改正では、再生資源の利用義務化が大きなポイントだ。製品単位で利用を義務付け、製造業者には再生材使用計画の提出と定期報告が義務化される。加えて、解体・分別のしやすさや長寿命化設計を評価する「環境配慮設計」認定制度も新設された。
資源循環の担い手として、回収や再資源化に積極的に取り組む事業者に対しては、廃棄物処理法の特例措置が与えられ、適正処理を前提に許可不要となる。シェアリングサービスなど、サーキュラーエコノミー型の新興ビジネスにも初めて明確な制度枠が設けられた。
この法改正は、単なる環境対策にとどまらない。あらゆる産業にとって、脱炭素と資源循環を軸にした「新しい成長戦略」としての転換が求められている。企業は排出管理の精緻化、製品設計の見直し、再資源化の高度化といった実務レベルでの対応を迫られ、自治体も地域循環型経済や産業支援のあり方を再考することになるだろう。
「気候変動への対応」から「環境を梃子(テコ)にした産業変革」へ。日本の法制度は今、明確にその方向へ舵を切った。2030年、そして2050年を見据えた本格的な移行期は、すでに始まっている。
法律案概要
https://www.meti.go.jp/press/2024/02/20250225001/20250225001-1.pdf
