旅行は楽しい。だが、自治体や街に負荷もかける。9月25日=SDGs採択の日に合わせ、旅行アプリ「NEWT(ニュート)」が全国1,741自治体から「サステナブルツーリズム」先進自治体TOP30を発表した。評価軸は環境、地域経済、文化継承、インクルーシブ観光、SDGs推進力の5項目。ランキングは民間の独自調査だが、観光公害や気候危機が現実味を帯びる今、地域と旅の関係を見直す格好の“地図”になる。

観光は「消費」から「再生」へ。世界の潮流と国内の基準整備。
観光は地球温暖化の主犯ではない。それでも無縁ではない。過去には、観光の全温室効果ガス排出が世界の約8%に達するとの推計がある(2009〜2013年、旅行・土産・食などを含む広義のフットプリント)。また観光需要の拡大に伴い、2009〜2019年の10年で観光由来のCO₂排出は年平均3.5%増え続けたとの最新分析も出ている。持続可能性は“気の持ちよう”ではなく、実装の課題だと言える。
国際的には、UNが2015年9月25日にSDGsを採択し(17の目標)、その後、観光分野でも国際基準の整備が進んだ。日本でも観光庁がGSTC(グローバル・サステナブル・ツーリズム協議会)の基準を土台に「日本版持続可能な観光ガイドライン(JSTS-D)」を整備。地域(デスティネーション)と事業者にとっての“共通言語”が用意されつつある。
NEWTの「TOP30」は何を映すか。現場の工夫、循環の設計。
【サステナブルツーリズム先進自治体TOP30】
1位:熊本県 阿蘇市
2位:宮城県 東松島市
3位:長野県 白馬村
4位:岐阜県 白川村
5位:徳島県 上勝町
6位:愛媛県 大洲市
7位:香川県 小豆島町・土庄町
8位:栃木県 那須塩原市
9位:群馬県 みなかみ町
10位:徳島県 三好市
11位:北海道 下川町
12位:京都府 南丹市美山町
13位:香川県 丸亀市
14位:北海道 美瑛町
15位:岩手県 釜石市
16位:東京都 小笠原村
17位:鹿児島県 与論町
18位:山形県 鶴岡市
19位:長野県 小布施町
20位:福岡県 太宰府市
21位:三重県 鳥羽市
22位:奈良県 十津川村
23位:長野県 松本市
24位:埼玉県 飯能市
25位:富山県 上市町
26位:千葉県 君津市
27位:山形県 西川町
28位:岩手県 大船渡市
29位:奈良県 奈良市
30位:鹿児島県 奄美市
NEWTのランキングは、①環境への配慮 ②地域経済への貢献 ③文化・伝統の継承 ④インクルーシブ観光 ⑤未来性・SDGs推進力を各100点で評価したという。たとえば阿蘇市は観光と草原保全を結びつけた仕組みで首位に。観光客が支払う“保全料”が千年の草原を守る財源になる設計だという。東松島市は震災復興をSDGs視点で再構築し、国際的な表彰の対象に。白馬村や白川村のように、国際認証やアワードを目標に据え、自治体・事業者・住民が一体で磨き込む地域も増えている。外部の客観指標を使い、地域内に対話と改善サイクルをつくるやり方だ。
こうした流れは世界の潮流とも重なる。UNWTO(現 UN Tourism)の「Best Tourism Villages」に日本の地域が選ばれ、Green Destinationsの「Top 100」に国内の自治体が入る事例も出てきた。国際枠組みの“ものさし”で自分たちを測る──地道だが効く。



ランキングの“落とし穴”。数字だけでは見えないものとは?
注意したいのは、ランキングが万能ではないこと。評価軸の重みづけ、データの取得方法、期間設定で結果は変わる。NEWTの調査は民間の独自評価であり、統計的に厳密な全国比較=公式序列ではない。だが価値はある。視察先のリストとして機能し、他地域が真似できる要素(保全料の組込み、分散型ホテル、ゼロ・ウェイスト、ユニバーサルビーチなど)を抽出できるからだ。
現場を見ると、成功地域ほど「観光収入の使い道」を明快にしている。自然保全、文化継承、移動の電動化、地域人材の育成に再投資する。観光客は「消費者」から「出資者」へ。旅行者の一票=予約・購入・参加が、まちの将来像に直結する設計が求められる。
旅人の実践リスト──“いい観光地”を選び、“いい行動”を足す。
観光の負荷は避けられない。ならば減らし、価値を上乗せする。基本は3つ。
①選ぶ
環境配慮や文化継承の方針を公表し、第三者指標(JSTS-D/GSTC、Top100、BTVなど)を活用する地域・事業者を選ぶ。
②移動・滞在を最適化
混雑を避け、公共交通やモビリティの電動化・再エネ導入に取り組む地域を優先する。現地で長めに滞在し、地産品・体験に支出を回す。観光のCO₂は移動が大半を占める。距離と回数を減らし、滞在時間と質を上げる。
③還す
保全料や文化財修繕への寄付、地域ガイドの利用、持ち帰らない・捨てない行動。ゼロ・ウェイスト拠点では分別体験に参加する。地域のルールに従い、SNS投稿の前に「場所を守る」視点を足す。
9月25日は、2015年にSDGsが採択された日だ。記念日の“正解”はない。だが、次の旅を選ぶ視点にSDGsを差し込むことはできる。NEWTのリストは、そのための素直な“入り口”になる。
観光は地域の鏡。数字やアワードに一喜一憂するより、現場の工夫と循環の設計に注目したい。旅行者の選択が、まちの未来を太くする。ランキングは、その選択を助ける羅針盤にはなる。
出典・参考:
UNが2015年9月25日にSDGsを採択(国連資料)/観光の排出量分析(Nature Climate Change 2018、Nature Communications 2024)/観光庁とGSTCに基づく国内ガイドライン(JSTS-D)/UNWTO Best Tourism Villages、Green Destinations Top 100 の日本事例。
あわせて読みたい記事

【新しい観光の在り方】八ヶ岳の森を“学ぶ旅”へ。植物と循環を体感する研究拠点「TENOHA TATESHINA Lab.」の価値を考える。

JALが始めるサステナブルツーリズム「Donate&Goコンソーシアム」
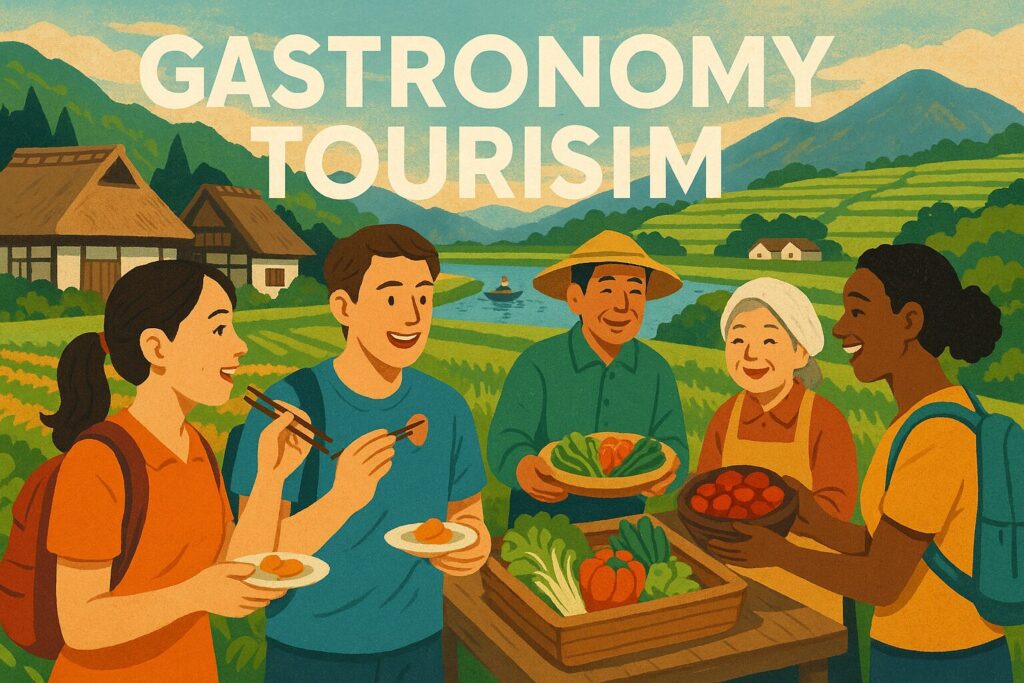
「食」が地方を変える。観光庁が進める「ガストロノミーツーリズム」とは何か?

【ネイチャーポジティブの始め方】岡山県真庭市発。「ネイチャーポジティブ」を政策・学術・ビジネスの視点から学び、実際の地域フィールドで行動に移す「蒜山ネイチャーウィーク」の10月。
