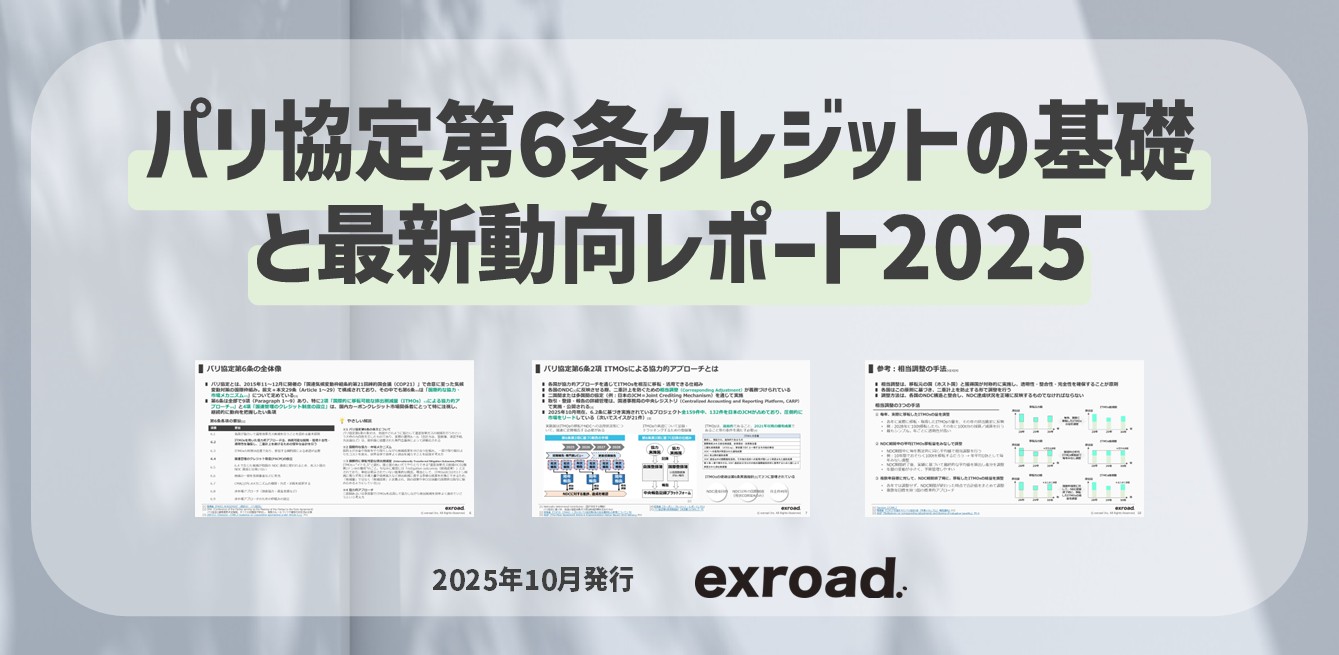
★要点
カーボンクレジットのデータベースを提供するexroad社が、企業の脱炭素戦略の羅針盤となる「パリ協定第6条クレジットの基礎と最新動向レポート2025」を公開。国境を越えたCO2削減プロジェクトの成果を誰のものとするか、その会計ルールである「パリ協定6条」、特にクレジットの二重計上を防ぐためのキー概念「相当調整」を、COP30を前に分かりやすく解説する。
★背景
2050年カーボンニュートラルに向け、企業は海外での再エネ導入や植林といったCO2削減プロジェクトへの投資を加速させている。しかし、その削減貢献を自国の目標達成にカウントするための国際ルールは複雑で、いまだ発展途上だ。ルールを理解せずに行うGX(グリーン・トランスフォーメーション)投資は、将来的に資産価値を失うリスクを孕む。
企業の脱炭素は、もはや国内だけの話ではない。国境を越えたCO2削減競争が本格化する中、その国際的な“ゲームのルール”を定めた「パリ協定6条」はCOP29で運用ルールが大枠合意され、実装段階に入った。ルールを理解し、制する者は誰か。COP30を目前に控え、企業のGX戦略の成否を分ける、複雑なルールブックの読み解きが今、求められている。
あなたの会社のCO2削減は、誰の手柄になるのか
「パリ協定」という言葉は知っていても、その「第6条」までを正確に理解しているビジネスパーソンはまだ少ないだろう。しかし、これは企業の脱炭素活動の価値を決める、極めて重要な国際会計ルールだ。 核心は、国境を越えて実施したCO2削減プロジェクトの成果(カーボンクレジット)を、誰が自国の削減目標(NDC)達成のために使えるか、という点にある。例えば、日本企業がベトナムで再エネ発電所を建設し、CO2を100トン削減したとする。この「100トン」は、日本の目標達成のために使うのか、それともベトナムの目標達成のために使うのか。もし両国が同時に計上すれば、「二重計上」という不正が生じる。 これを防ぐためのルールが「相当調整(Corresponding adjustment)」。日本がこの100トンを使うなら、ベトナムは自国の削減量から100トンを差し引かなければならない。この複雑な調整メカニズムの理解こそが、グローバルな脱炭素投資の第一歩となる。
COP30の焦点、「NDC適用期限問題」という時限爆弾
今回exroad社が発行したレポートが警鐘を鳴らすのが、「NDC適用期限問題」だ。多くの国は、削減目標(NDC)を「2030年まで」といった期間で設定している。では、2031年以降に発行されたクレジットは、2030年までの目標達成に使って良いのか。 この問いに対する国際的な合意は、まだ完全に形成されていない。もし「使えない」となれば、日本が推進するJCM(二国間クレジット制度)などで、2030年以降の長期的な投資回収を見込んでいたプロジェクトは、その価値を大きく損なうリスクを抱える。 2025年11月にブラジルで開催されるCOP30では、この問題が主要な議題の一つとなる可能性が高い。企業の担当者は、自社が関わるプロジェクトのクレジットが、いつ発行され、どの目標期間に適用されるのかを、契約書レベルで再確認する必要があるだろう。難解な専門用語の向こう側で、自社の資産価値が静かに揺らいでいるかもしれないのだ。
ルールを制する者が、GXを制す
パリ協定6条を巡る議論は、単なる環境政策の話ではない。それは、カーボンクレジットという新しい資産の価値を定義し、GX-ETS(排出量取引制度)のような国内市場の動向にも直結する、経済安全保障の問題でもある。 今回のような専門的なレポートを読み解き、国際ルールの潮流をいち早く掴むこと。それが、これからの時代に企業が持続的な成長を遂げるための、不可欠な羅針盤となるだろう。
ホームページはこちら
あわせて読みたい記事

【気候変動とビール】キリンの新技術──ホップ苗に高温・乾燥耐性を与える世界初のアプローチ。

【白州で“つくって、燃やす”水素循環】日本最大16MWのP2G、サントリー天然水・ウイスキーの熱源を水素に——「グリーン水素パーク -白州-」始動

【アフター大阪・関西万博】万博パビリオンのテント膜が、街で持ち歩くプリーツバッグに——山口産業の「廃棄ZERO」実装
