京都大学と住友金属鉱山が共同で開設した「住友金属鉱山二酸化炭素有効利用産学共同講座」において、CO₂を高効率でCO(一酸化炭素)に変換する紫外光応答型光触媒が開発された。変換効率は従来比約30倍に達し、プラスチック原料などへの応用が期待される成果である。化石燃料に依存しないカーボンニュートラル社会の実現に向けたブレイクスルーとして注目されている。
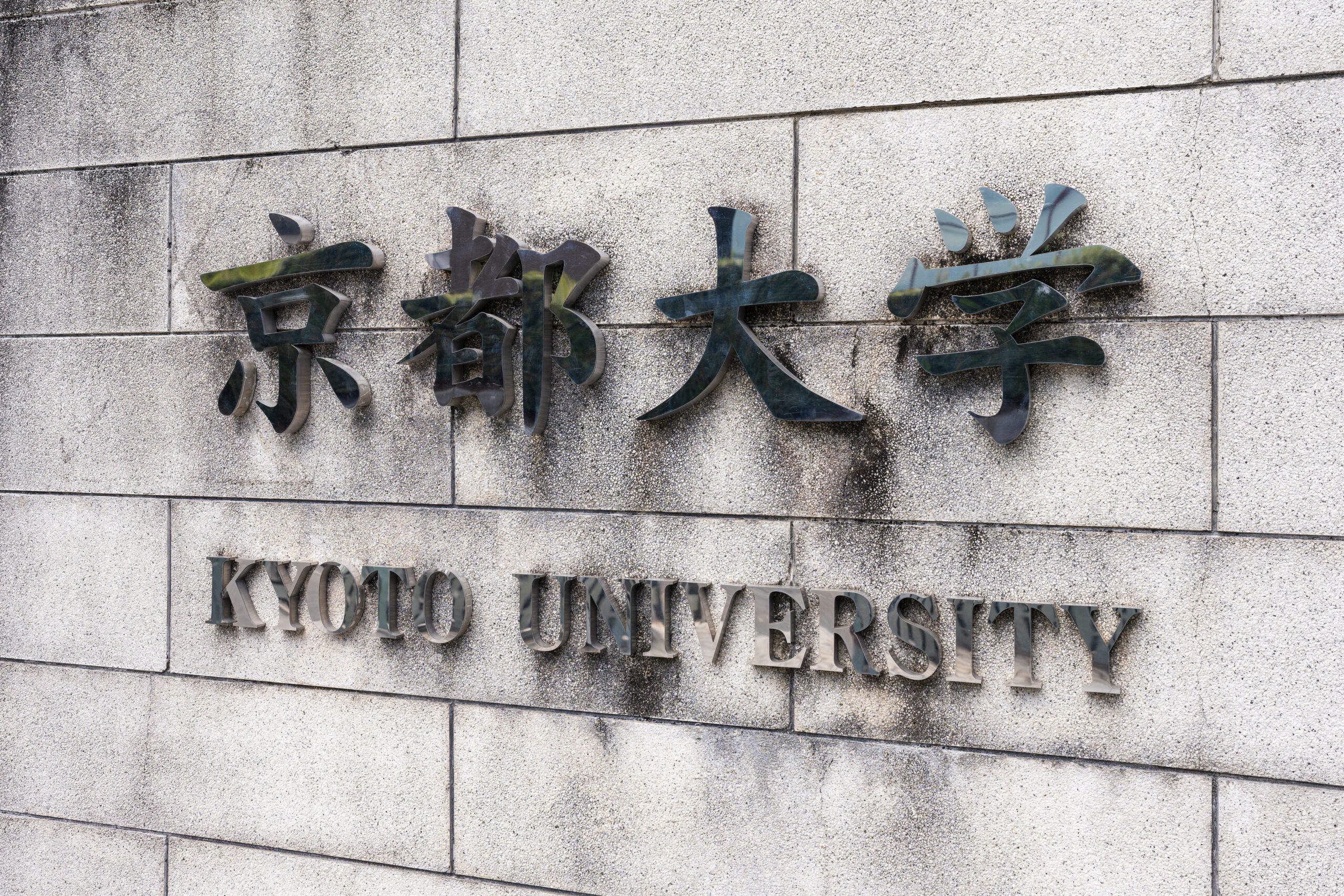
「人工光合成」実用化へ。CO₂をCOに変える鍵は、光と触媒の融合技術。
温室効果ガスである二酸化炭素(CO₂)を、資源として再活用する。そんな未来を切り拓く鍵として期待されているのが、光エネルギーによってCO₂を有用物質に変換する「人工光合成」技術だ。しかし、CO₂は化学的に極めて安定な分子であり、これを効率良く変換するのは技術的な難題だった。
こうした状況を打開すべく、京都大学大学院工学研究科寺村研究室と住友金属鉱山は、2022年6月に共同講座を設置。両者の技術を融合し、従来にない高性能の光触媒材料の開発に挑んできた。今回開発されたのは、半導体材料「タンタル酸亜鉛(ZnTa₂O₆)」に銀(Ag)ナノ粒子の助触媒を担持し、さらにその表面にクロム化合物をコーティングした構造。この手法によって、光還元によって得られるCO濃度が従来の270 ppmから一気に8,000 ppm超へと引き上げられた。これは世界的にも類を見ない水準だ。
エネルギー資源としてのCO。光触媒によるCO₂循環型社会への展望とは?
CO₂をCOに還元する技術は、単なる排出抑制にとどまらず、循環型の炭素利用システムの中核を担う。COはプラスチックや化学製品の原料として用いられる重要な工業用ガスで、その製造過程においてCO₂から直接得られるのであれば、化石資源の使用量を大幅に削減できる。
今回の研究で確立されたのは、住友金属鉱山の粉体合成・表面処理技術と、京都大学の触媒設計ノウハウとの高精度な融合である。Agナノ粒子の分散性と担持方法を最適化し、超音波還元法と呼ばれる手法を導入することで、従来を大きく凌駕する変換効率を実現した。
今後は、光触媒材料の改良を通じて、より波長の長い可視光でも反応する触媒の開発が課題となる。現状では300nm以下の紫外光のみが利用可能だが、太陽光の大部分を占める可視光領域に対応できれば、実用化への道はさらに現実味を帯びるだろう。
2025年以降を見据えた技術融合。カーボンニュートラルへの加速装置となるか?!
この成果は、国際学術誌『ACS Catalysis』の2025年2月号に掲載され、国内外の研究者からも大きな関心が寄せられている。研究の根幹をなすのは、企業と大学が対等な立場で技術融合を図る産学連携のあり方であり、その成果は「脱炭素社会のための基盤技術」としての可能性を存分に示した。
京都大学と住友金属鉱山は今後、光触媒によるCO₂還元のさらなる性能向上とスケールアップに取り組む方針だ。目指すは2050年のカーボンニュートラル社会。この光触媒技術はその時限に向けて、“エネルギーと環境の両立”を実現する象徴的な存在となる可能性を秘めている。
