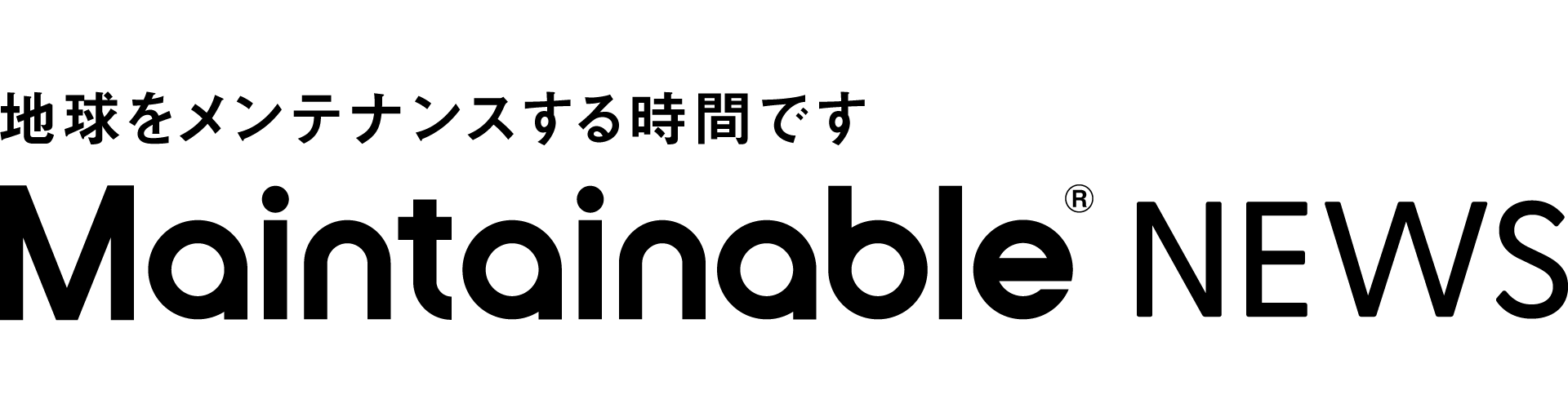遠藤 謙一良さん/建築家 株式会社遠藤建築アトリエ 代表取締役社長
現代建築から地域性再生と木造建築への回帰へ
いま日本は森と生きる時代に入っている。植樹した樹々の伐採利用、CO2の吸収源整備、心身再生のためのデザインゾーン作りと、官民にさまざまな動きが出始めている。そして人が暮らし、働き、憩うための空間としても、木材を使った木造建築が再び新しい日本建築の潮流を生み出しつつある。木の建築家である遠藤謙一良さんに話を聞いた。
遠藤 僕が建築家を志した時代は、近代建築の終わりと新しい波の始まりの頃でした。近代建築の大家、丹下健三さんの影響が色濃く残るなかで、建築界では多様性と地域性への関心が高まっていました。
この時代の変化は、建築教育にも新たなテーマをもたらして、僕たちの学生時代を形づくっていきました。ディスカバージャパンのようなムーブメント、安藤忠雄さんの都市ゲリラ活動などが、僕たちに新たな視点を与えてくれましたね。
― そこから遠藤さんの建築家活動が始まった。
遠藤 はい。加えてジャーナリズムや学問の世界では、世の中の出来事に対して多様な価値観を見直そうという動きがありました。
文化人類学を含むさまざまな学問分野で、モダニズムの後のポストモダンという大きな流れも生まれていましたし、この流れは多様なものに対する価値を見直して、社会価値をもう一度見直す機会を与えてくれたと思います。
そういう流れの中で見えてきたのが、「地域性の再生」です。地域の文化を国際化するのではなく、多様化することが新たな価値になってきた。人間の身体感覚をもう一度見つめ直すことも、この時代における大事なテーマでした。
― 「木」に対する視点が生まれたのは?
遠藤 この時代の変化の中で、僕も学校などで木造について教える機会が増えていったのですが、実は木造建築についてはあまり経験が無かった。けれど教えなくてはならない。なので自分自身も再学習しながら、縄文の世界や氷河期以降の地球の大きな変化の中での生き方や、人間の定住の始まりについて理解を深めていったのです。そして木造そのものの源流が、アジアや日本の深い部分にあることを学びました。
― 縄文の世界の学びがヒントになった?
遠藤 専門書を読んでいくと縄文の歴史は1万5千年ぐらいまで遡れるんですけど、その頃から恐らく木造文化はスタートしていて、なおかつ「定住」という事が起きてきた。その定住は氷河期以降のことですから、まだ非常に寒かったり地球が安定を始める中で、地球の資源と対話をしながら暮らしていたと思います。北海道でも函館地域で定住跡が出ており、6000年間、人々が集団で生き続けたのは凄いことです。
恐らくそこには何かのルールや、何がしかの発見があったのだと想像できますし、それらが全て「木造」ということに帰結したんです。
― どういうことですか?
遠藤 気候が木造建築をもたらしたのではないかということです。亜寒帯性湿潤気候に属する北海道では、札幌だと平均気温は9.2~3℃。地面を8メートルほど掘っていくとこの平均気温の場所になります。
そこで縄文の人は地面に穴を掘り、竪穴式住居をこしらえた。そうすることで安定した気温が得られるからです。
やがて人々は大きな発見をします。それは壁のない「屋根建築」です。住居空間を暖めるために「火」を使うのですが、この「火」を守るために「屋根」を作り、非常に安定的な火を作って、同時にこの火を使い食べ物を縄文土器で煮物にしながら食べ続け、同時に火により地面を暖め蓄熱され輻射暖房となる温熱環境をつくりました。

遠藤謙一良さんの建築作品の一つ、羊蹄山を正面に望む畑の一角に建てられたレジデンス「ヨウテイ ファームハウス」(北海道・倶知安町)。落雪屋根を支える木構造(登梁)が表された2階の大空間が住まいを包み込む。第9回「北の聲アート賞」(アウラ賞)受賞/2023年
― 火を守る屋根を木で作り、人は竪穴式住居を進化させていった。
遠藤 この場所で暮らしながら、自然の営みや宗教的なものも含めて精神的な世界観を作って、文化や社会を作ったのだと思います。
そしてこれらを実現させたのは何かと言えば、四季です。当時も北海道は雪が降ったでしょうし、雨があって、春には木が芽吹き、この移り変わりを人々はもの凄く観察したと思います。
春の芽吹きが、夏にたわわに実り、秋に収穫してという植物の連鎖の流れも当然理解したはずだし、これらがやがて懐石料理に繋がったり、あるいはお祝いとか慶びとか怖れにも繋がり、これらの進化を支えたものが木造文化なんじゃないかと。これを形として儀式化したのが、伊勢神宮の式年遷宮だと思われます。
― 木の文化の国と石の文化の国。その違いも気候風土の差異。
遠藤 そうですね。建築家の視線で見ても明らかにヨーロッパのような石の文化で固定される世界と、循環させていき、そこに生活と文化そのものを捉えていく日本の感覚は真逆の世界です。そこでの社会継続性と建築教育における日欧の根幹的な違いも、この気候風土に根差していると思います。
そして日本で建築を手がける以上、やはり木造化しながらその地域の自然と一体化して生きていける感覚が最もシンプルなことだし、素敵な生きかたが出来るんじゃないだろうかということが、僕が木造建築をスタートした経緯でもあります。
― 遠藤さんが志す木造建築と、齊藤雅也さんが実践している「室内気候デザイン」との出会いも、そんな縄文から繋がる北海道の気候風土への再認識が理由と言えますか?
遠藤 そうなんです。僕は小樽で生まれて北海道に居ますから、子どものころからニセコにもよく行っていて、たぶんニセコの価値は日本でも屈指だなと感じていました。
ですので自身の建築テーマも木造建築にシフトチェンジし、自身のアトリエを作る段になった際に、北海道の気候はだいたい春から6月ぐらいが最高に気持ちいいのですが、これを空間で実現したいと思いました。
そこで、札幌市立大学で室内気候デザインの実践成果を上げられていた齊藤教授と相談し、北海道の快適な気候の魅力を最大限に建築で引き出そうと決めたのです。
― 遠藤さんのアトリエは室内の空気の流れが気持良いし、特に冬場にお邪魔した時には「北海道の寒気の中で、こんな省力のボイラーでこんな暖かくて快適なの?」と、何度も聞き返しましたよね(笑)?
遠藤 (笑)。床下の外断熱された基礎とスラブのコンクリートの蓄熱力を活かし壁の高断熱、室内の空気の流れを、室内気候の分析と建築デザインによって、新しく可能にできることを形にしました。
そこに居る皆が「ああ、いいね」とか、皆が自然体でその環境価値を共有できるようにクリエイティブすることで、環境と融合した独自の文化が地域に根付く事を願っておりますし、自分の実践としては住宅も含めて小さい単位からそういった空間を実現したいなと思っています。
― 「木造建築×室内気候デザイン」はこれからの空間づくりの潮流になる予感がします。
遠藤 感覚的に五感で響くような空間に人間がいるのが一番幸せだと思うんです。それを実現できつつある気候に融合した北海道建築は、気候変動時代の新たな切り札としても活用できるはずですし、日本全国に知っていただきたい建築デザインです。
またそこでどんな木を使うのかもとても重要なことです。
― 木を選ぶ?
遠藤 木造建築は、単に美しいだけでなく実用性も兼ね備えています。日本の伝統建築、特に京都の数奇屋建築から受け継がれるデザインの要素を現代的に解釈し、それを私も木造建築に取り入れています。木造建築における自然との対話、四季の変化を反映することが、これからの建築における大きなテーマです。
これを本州では檜や杉などで行ってきました。じゃあ北海道の木だと何になるのか。それは、エゾマツだということが分かりました。
― 森から生み出す建築というわけですね。
遠藤 はい。北海道の原種はエゾマツとトドマツしかないんです。カラマツは長野から持ってきた、杉は本州からもってきた、ということで4大針葉樹になっています。ですがエゾマツは伐木の単位が80年から100年級にならないと切れないしなかなか育ちにくく、植林技術が誕生してまだ30年しか経っていません。残念ながら流通していないんです。
しかし丹念に探していったら、東大の演習林にエゾマツの原生林の伐木が残っていることが分かり、それを払い下げていただき今回の地産地消の建築を実現しました。
それぞれの土地の気候風土に合った木造建築を実現するためには、それぞれのエリアの植生についての知識も重要です。