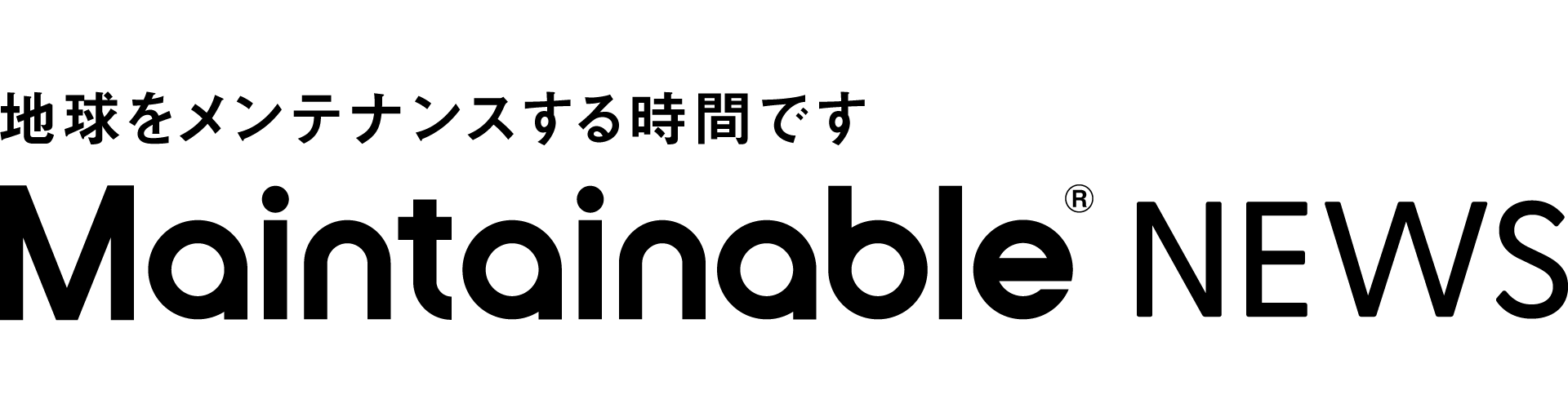★要点
環境省グッドライフアワード『EXPO2025いのち動的平衡賞』を受賞した「罠ブラザーズ」は、罠シェアリングを通じて、都市に暮らす人が“狩猟から食卓まで”を追体験できるコミュニティだ。鹿の個体数増加という現実と向き合いながら、ジビエを「買う」のではなく「いただく」プロセスごと共有し、人と野生と地域経済をつなぎ直そうとしている。
★背景
気候危機と生物多様性の損失が進行し、世界人口の約7割が都市に暮らす時代が目前にある。自然から切り離された生活のなかで「命を食べる」感覚は薄れ、一方でシカの増加による農林業被害や生態系の乱れは深刻化している。課題を“外注”するのではなく、市民が当事者として関わる仕組みづくり——その一つの答えとして、罠ブラザーズの挑戦が立ち上がっている。
スーパーのパック肉を手に取るとき、その一歩手前で何が起きているのか。山で仕掛けられた罠、しとめられた鹿の体温、血の匂い、解体の手仕事——私たちはそのほとんどを知らないまま日々を食べている。
「罠ブラザーズ」は、その見えないプロセスを丸ごと都市に運び込む試みだ。罠の設置から解体、ジビエを味わうまでを“共有”することで、食卓と山、都市生活と野生のあいだに、新しい橋を架けようとしている。
街にいながら山とつながる。「罠をシェアする」という参加のかたち
罠ブラザーズは、ジビエ肉のサブスクでも、単なる産直サービスでもない。核にあるのは「罠シェアリング」という発想だ。
長野県上田市の猟師たちが山にかけた罠を、都市のメンバーがオンライン上で“シェア”し、その罠にかかった鹿が解体され、ジビエとして届けられる。肉だけを受け取るのではなく、「どの山で」「どんな経緯で」その命が捕らえられたのかまでを追体験できるよう設計されている。
罠が鳴らす通知は、山の時間が都市の生活に割り込んでくるサインでもある。会員はレポートや映像、現地イベントを通じて、猟の現場とつながる。
冷蔵庫の中で完結していた“食”に、地形や季節、獣の習性、人の技が立ち上がる。都市の台所と山の稜線が、デジタルを介して一本の線で結ばれる感覚だ。

鹿が増えすぎた森で起きていること。“美味しい”の裏側にある課題
罠ブラザーズが相手にしているのは、グルメ雑誌的な「ジビエブーム」ではない。
狩猟が担い手不足で縮小する一方、鹿は個体数を増やし続ける。若い木の樹皮が食い荒らされ、下草は消え、森の更新力は落ちる。畑は荒らされ、農家は防護柵や忌避対策に追われる。山の生態系と農林業へのダメージは、すでに「どこか遠くの話」ではない。
こうした現実のなかで、鹿を一頭しとめることは、単なるレジャーではなく、地域を維持するための仕事になりつつある。
罠ブラザーズは、猟師の活動を経済的にも精神的にも支える仕組みとして構想された。ジビエを購入するだけでなく、その背景にある「害獣管理」や「森づくり」まで含めて共有することで、消費行動を“共創”に変えていく。
「おいしいジビエ」の前提には、森の健全さがある。罠ブラザーズは、舌の満足と同時に、その前段にある問題の存在を隠さない。むしろ、そこから目をそらさないことを価値に変えようとしている。

“僕たちはどう食べるか”を問い直す。ツアーと年間プランがつくる関係の厚み
オンライン上の罠シェアリングに加え、罠ブラザーズは現地での食体験も重ねている。
長野県上田市で開催される「僕たちはどう食べるか ツアー」は、その象徴的なプログラムだ。参加者は1泊2日で猟師と山や畑を巡り、自分たちが日々口にしている命が、どのようなプロセスを経て食卓に届くのかを、五感を総動員してたどっていく。
山を歩き、罠や足跡を見つけ、解体の現場を間近で見て、最後にジビエを味わう。
「美味しい・美味しくない」の前に、「いただくとは何か」という問いが立ち上がる。自然のなかでの時間と、解体の手触り、食卓の静かな緊張感。その全部をひっくるめて一つの“食体験”として構成している点に、このプロジェクトの骨太さがある。
一方で、年間を通して鹿肉が届く「アメイジング・罠ブラザーズ」のようなプランも用意されている。
単発の“イベント”で終わらせず、季節ごとの変化や猟期のリズムを、自分の生活リズムに重ねながら受け取る仕組みだ。冷凍庫を開けるたびに、山の時間がふとよみがえる。関係性を点ではなく線でつくることで、「忘れない」ための装置にもなっている。


土とデジタルのあいだで——都市にバイオフィリックな回路を埋め込む
罠ブラザーズを運営する「土とデジタル」は、自らをバイオフィリック・スタジオと名乗る。自然とテクノロジー、野生と都市生活、一見対立するように見える要素を、補い合う関係として捉え直すことを掲げている。
背景には、2050年までに世界人口の約68%が都市に居住するという予測がある。都市のふるまいこそ、これからの地球の行方を決める。そう考えるなら、オフィスワークやリモート会議に追われる日常のなかにこそ、自然への敬意や地域との接点を埋め込む必要がある。
罠ブラザーズは、そのための“実験装置”の一つだ。
予約フォームやオンライン決済、SNSでの発信といったデジタル技術は、都市の生活者にとってのハードルを下げる。一方で、最終的に受け取るのは、血の通ったジビエと、山の空気と、猟師の暮らしの物語である。
テクノロジーは、自然体験を代替するのではなく、そこへ至る回路を増やすためのインフラとして使う。
「土」と「デジタル」を行き来しながら、都市生活の文脈のなかに野生との接点を差し込む。この二重構造こそが、罠ブラザーズの骨格であり、他の産直サービスとの決定的な違いでもある。
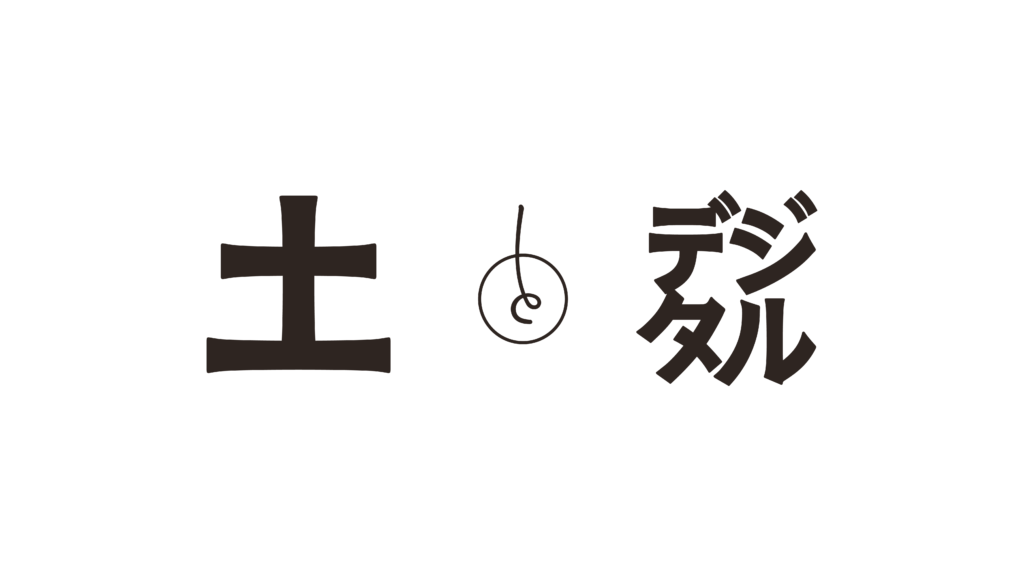
賞が照らしたのは“ジビエ”ではなく、“生き方のアップデート”
今回、罠ブラザーズが受賞した環境省グッドライフアワード『EXPO2025いのち動的平衡賞』は、「環境と社会によい暮らし」を評価軸とし、地域循環共生圏=ローカルSDGsの実践を後押しする仕組みだ。
評価されたのは、鹿肉そのものの美味しさだけではない。
・増えすぎた野生動物との距離をどう取るか
・自然資源を“消費”ではなく“関係”として扱えるか
・都市生活者が責任と喜びをシェアできる設計になっているか
こうした問いに対して、罠ブラザーズは一つの回答を提示した。狩猟をロマンチックに美化するのでも、過度に道徳化するのでもなく、「具体的な行動と選択肢」として提示している点が、賞の名前にある「いのちの動的平衡」というコンセプトと響き合う。
環境負荷の小さいメニューを選ぶことや、プラスチックを減らすことも確かに大事だ。だが同時に、「そもそも自分は何を食べ、どんな死を通じて生きているのか」という根源的な問いから逃げないことも、持続可能性の重要なレイヤーである。
罠ブラザーズは、その問いを一人で抱え込ませない。猟師、参加者、運営チーム、地域の人びと——複数の主体が関わるコミュニティとして支えることで、「食べる責任」を孤立させず、連帯の感覚に変換している。
街のレストランで鹿肉を味わうとき、そこに「罠」と「山」と「猟師」の姿を重ねる人が少しずつ増えていく。
その小さな変化の積み重ねが、気候危機と生物多様性の損失の時代を生きる、私たちのライフスタイルを静かに更新していくはずだ。
ホームページはこちら
あわせて読みたい記事

SUPER EIGHT安田章大、アイヌ文化と出会う旅――「Wonder Culture Trip ―FACT―」が大晦日に放送

クマとの境界が消えゆく。「鳥獣保護管理法」改正案と人と自然の共生をめぐる課題。

【新しい観光の在り方】八ヶ岳の森を“学ぶ旅”へ。植物と循環を体感する研究拠点「TENOHA TATESHINA Lab.」の価値を考える。