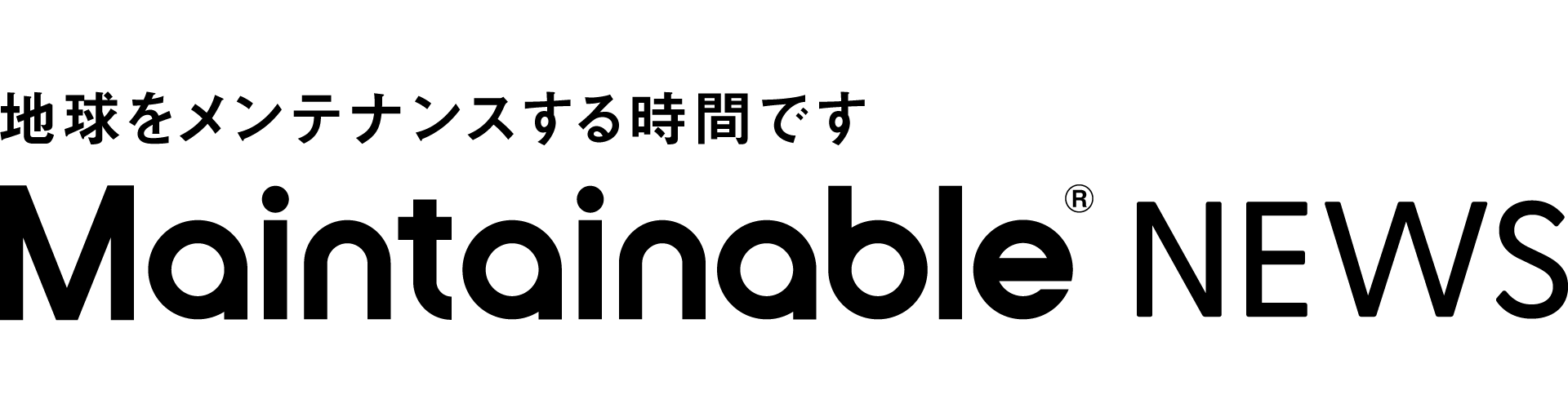★要点
魚粉に偏った養殖飼料を、昆虫タンパクで“分散”する。ミールワーム粉末を飼料の10%に配合し、マダイの成長・嗜好性・健康・味まで多面的に検証する共同実証が動き出した。
★背景
気候変動と地政学でサプライチェーンが揺れ、輸入依存の原料は一気にリスク資産になる。養殖コストの大半を占める飼料の不確実性は、そのまま“食卓の不確実性”だ。
養殖は「増やせば解決」ではなくなった。増やすための餌が、世界の不安定さに直結しているからだ。魚粉は高い。つまり揺れる。奪い合いも起きる。そこで浮上してきたのが昆虫タンパクという選択肢だ。ミールワーム粉末を使った共同実証は、単なる新素材のニュースではない。日本の養殖が、供給網と気候の変動に耐える“設計”へ移れるかどうか。その試金石だ。
「餌代が6〜7割」——養殖の弱点は“魚の外”にある
国内養殖の収益構造を一言で言えば、飼料の比重が重すぎる。生産コストの6〜7割を飼料代が占めるという現実は、経営努力だけでは吸収しきれない外部変動を抱え込むことを意味する。
しかも主原料の魚粉は輸入依存度が高く、価格高騰や供給網のリスクが顕在化している。さらに魚粉の原料自体が天然資源に依存する以上、「持続可能性」という問いから逃げにくい。
気候変動で海が変われば、漁業も養殖も同時に揺れる。回遊資源が動き、ルールが追いつかないリスクが語られるいま、海のタンパク供給を支える“入力”(飼料)をどう再設計するかが、むしろ主戦場になってきた。
ミールワーム10%配合。“代替”より先に“検証の型”をつくる
今回の共同実証は、DNPが愛媛大学と進めてきたミールワーム粉末の研究を、配合飼料としての「実装検証」へ進める位置づけだ。2026年2月5日から、500L水槽8基で試験を行い、フィード・ワンが販売する飼料の10%をミールワーム粉末に置換したマダイ用飼料で評価する。
ポイントは、昆虫粉末を“入れてみました”で終わらせないことにある。加工条件を複数設定し、供給・製造プロセスまで含めて適性を見極める。評価項目も成長速度、摂取量、生残率、体成分、味に加え、健康状態やストレス指標、耐病性にまで広げる。
つまり、原料の物性や栄養だけでなく、「工場で作れて、現場で回って、魚が育ち、品質が成立するか」という一連の“型”を作ろうとしている。ここが成功すれば、昆虫タンパクは単なる代替原料ではなく、調達分散と機能性を同時に狙うオプションとして現実味を帯びる。


国産化の含意。食料安全保障は「在庫」ではなく「生産能力」で決まる
ミールワーム粉末の意義は、栄養価だけでは測れない。供給体制の設計が、食料安全保障のど真ん中に刺さるからだ。DNPと愛媛大学は2023年から、ミールワームの安定的な国内量産と、養殖飼料に活用するビジネスモデルを視野に共同研究を進めてきた。
今回の水槽試験は2026年4月まで実施し、5月以降は加温試験など機能性評価を追加する予定だという。さらに量産目標として、2028年度に年間100トン、2030年度までに年間1,200トンの生産を掲げる。
ここで問われるのは「作れるか」だ。輸入依存の原料は、平時は安く見えても、有事に跳ねる。気候と地政学の時代には、“価格”より“継続”が価値になる。在庫を積み上げる発想から、国内での生産能力・供給網・品質保証を整える発想へ。昆虫タンパクは、その転換を具体化しやすい領域の一つだろう。
“サステナブル”の次に来る宿題「コスト、規制、LCA」そして「味」
とはいえ、昆虫タンパクは万能薬ではない。まずコスト。飼料は「安定供給」だけでなく「安定価格」が要件になる。次に品質・安全性と規格化。量産すればするほど、飼育・加工条件のばらつきが課題化する。
さらに重要なのがLCA(ライフサイクル評価)だ。昆虫は資源効率が高いと語られがちだが、エネルギー投入や原料(餌)設計、加工・乾燥工程まで含めて“本当に得か”はケースで変わる。だからこそ今回の試験が、加工条件や供給プロセスまで含めて検証する設計になっている点は大きい。
最後は、消費者の舌と市場の信頼である。味の評価項目が明記されているのは象徴的だ。養殖は結局、食卓に届いて完結する。技術は魚の体内だけでは終わらない。
ミールワームは、魚粉の置き換え素材として語られてきた。しかし本質は、養殖を“外部ショックに強い産業”へ作り替えるための部品かもしれない。気候が揺れ、物流が揺れ、コストが揺れる時代に、食の強さは「どこで何を作れるか」に回帰する。水槽の中で起きているのは、魚の成長試験であると同時に、社会の耐久試験でもある。
あわせて読みたい記事

持続可能なサーモン養殖の未来を切り拓く

【マグロ・カツオ漁業×気候危機】“動く資源”に“動くルール”を――MSCが示す最脆弱リスクの正体