ファミリーマートが北陸3県(富山・石川・福井)の約550店舗で、弁当・おむすび・惣菜・デザートなど約800品目を運ぶ「定温便」を、2025年9月16日納品分から従来の1日3便から2便へ再編する。配送コースと納品時間帯を組み替え、年間走行距離は約150万km減、CO2排出は約3割減を見込む。あわせて長期保存できる冷凍弁当を導入し、販売機会と食品ロスの双方を抑え込む。

配送を“薄く速く”から“濃く正確に”へ――冷凍弁当と生産分担で需給を制御。
小売物流は、人手と燃料の逼迫、原材料高騰という逆風の中で、便数の多さがそのまま顧客価値に結びつかない局面に入りつつある。ファミリーマートは北陸エリアで定温便の2便化に踏み切り、頻度ではなく密度を高める設計に切り替える。ルート最適化と納品時間帯の再編で“空気を運ぶ”距離を削り、年間約150万kmの走行圧縮と約3割のCO2削減を狙う。店舗側では荷受けの山谷が平準化し、限られた人員での売場維持に寄与するはずだ。
製造サイドも同時に手当てする。北陸の米飯2工場が広く並行生産してきた約70品目を分担し、段取り替えのロスを減らす。これにより、供給の安定と品質均一、原価の抑制を同時に拾いにいく。便数を落とすだけでは欠品リスクが立ち上がるが、そのバッファとして長期保存が効く冷凍弁当を新設する。急速冷凍で品質を保持し、店頭で加熱提供する運用により、ピーク時の販売機会を補完しながら消費期限起因のロスを避ける意図だ。初弾は「こだわりデミグラスソースのデミオムライス」(税込498円)、「トマトの旨味あふれるナポリタン&海老ピラフ風」(同598円)、「旨味たっぷり炒飯&唐揚げ」(同550円)の3品を用意する。



移行の要は発注精度だ。店舗ごとの販売ピークと新しい納品タイミングに即した最適発注を支援するため、専用の発注支援ツールとスーパーバイザーの伴走で注文バランスの学習・補正をかける。現場の経験値とデータドリブンを接続し、欠品と廃棄の双方を最小化する狙いだ。
便数を減らすことは目的ではなく、走行距離と排出、廃棄と機会損失、現場の作業負荷――サプライチェーンの“目減り”に正面から切り込む手段だと考えられる。北陸での実装結果が良好なら、他地域への横展開も視野に入るだろう。社会のインフラとしてのコンビニが、環境負荷と採算性の交点を探る実験として、今回の2便化は注目に値する。
あわせて読みたい記事

ファミリーマート、新システム導入で店舗運営を省エネ革命

京セラとJR東日本が仕掛ける食のDX。アレルギー対応弁当「matoil」を東京駅でロッカー受取。

食材すべてを無駄にしたくない!吉野家の牛丼が挑戦する、「玉ねぎ端材のアップサイクル」と持続可能なスキーム
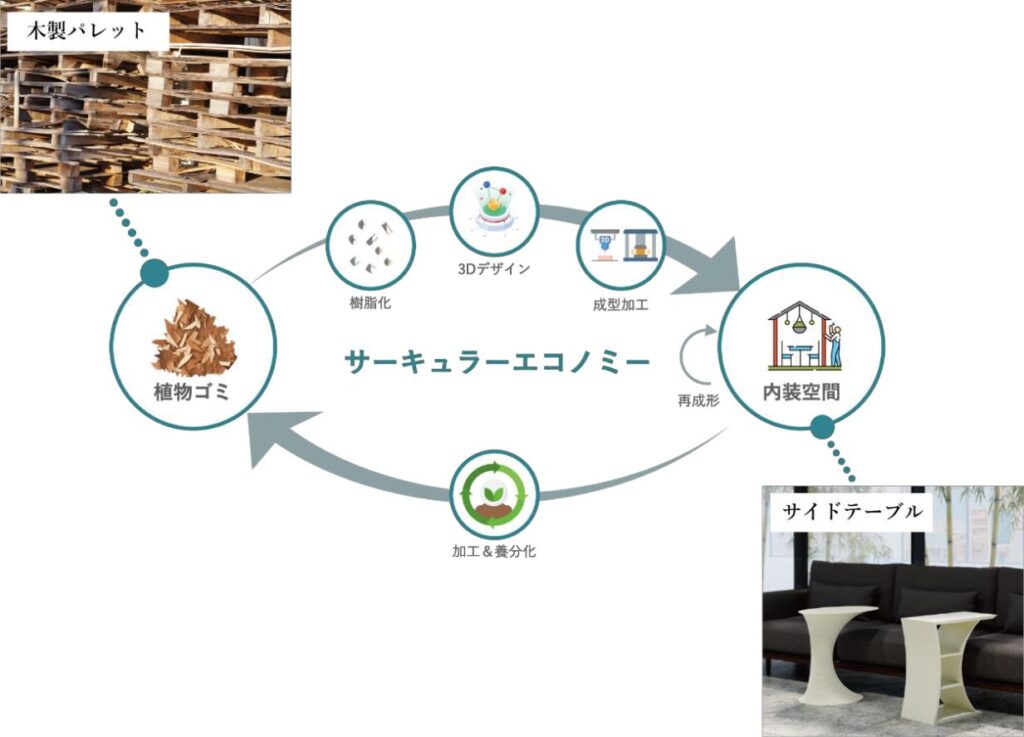
サステナブル物流の未来を切り拓く。セイノーHDとSpacewaspの植物由来アップサイクル実証とは?
