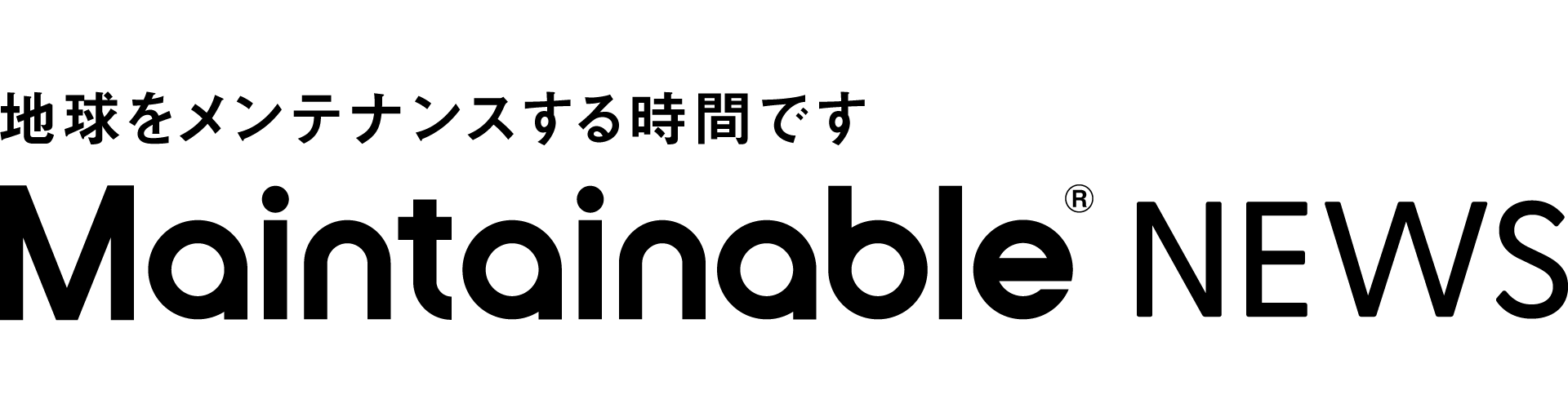★要点
大阪・関西万博のパビリオンで使われた中規模蓄電池(約200kWh)を、北海道最古の酒蔵・小林酒造の新蔵に移設。太陽光(55kW)と組み、酒造りの電力コストとCO₂を下げつつ、停電時のBCP電源にもする“レガシー継承型”モデルが動き出した。
★背景
脱炭素のボトルネックは技術不足より「導入の摩擦」だ。国際イベントの設備は会期が終われば廃棄されがちだが、再利用できれば資源と投資の目減りを止められる。災害や停電リスクも抱える地域では、再エネは“きれいな電気”である前に“止まらない電気”でもある。
万博は未来を見せる。だが、未来は会場の外に残らなければ意味がない。大阪・関西万博で稼働した蓄電池が、閉幕後に北海道の酒蔵へ移設されるという。舞台は、創業140年超をうたう小林酒造の「105年ぶり新築酒蔵」。万博の熱狂を、地域の現実——電気代、雪、停電、そして脱炭素——に接続する試みだ。レガシーとは記念碑ではない。使い続けて、価値を増やす仕組みである。
「閉幕後」に価値が出る——万博設備は“短命資産”になりやすい
大阪・関西万博は2025年4月13日から10月13日までの開催だった。
巨大イベントの宿命は、設備の寿命が会期に縛られる点にある。仮設であり、撤去が前提。だからこそ閉幕後には、まだ使える資産が“行き場”を失う。ここに循環の余地がある。
EUREKAが言う「万博レガシー継承型」は、この空白を埋める発想だ。中規模蓄電池システム(約200kWh)を、万博の中東大手国家パビリオンから小林酒造へ移設・再利用し、再エネシステムとして運用を始めたという。
レガシーの本質は感動の保存ではない。設備の再配置で、地域の支出と排出を同時に減らすこと。ここまで落とし込めて初めて「次の社会」に届く。
雪国の再エネ——積雪を前提に設計する
北海道で太陽光と言うと、すぐに「雪で発電できない」という話になる。半分は正しい。半分は古い。問題は“雪があること”ではなく、“雪を前提に設計していないこと”だ。
今回の新蔵では、積雪地の課題に対して、落雪をスムーズにする屋根一体型の太陽光(カナメ社のソーラールーフ)を採用したとされる。意匠と発電を両立し、雪の合間の日射も取りこぼさない狙いだ。
再エネは地域条件で顔が変わる。北海道では、機械より「屋根の設計」が勝負になる。ここを丁寧にやるプロジェクトは、地味に強い。

太陽光55kW×蓄電池200kWh。脱炭素は“自給”より“自律”へ
システムの骨格は「太陽光×蓄電池」だ。太陽光パネル出力55kW、蓄電容量約200kWh、最大出力100kW。日中に発電し、貯め、必要な時に使う。酒造工程の電力コスト削減に加え、「カーボンニュートラル」という付加価値を酒に載せるという。
ここで重要なのは、“完全自給”の誇示ではない。電力が不安定になる局面で、工場が自律できるかどうかだ。製造業の脱炭素は、理想としての再エネでは回らない。実務としての電力——止まらない、読める、管理できる——が必要になる。

BCPの主役は「発電」ではなく「優先順位」——麹室に電気を残す発想
北海道は2018年の地震で、エリア全域の大規模停電(ブラックアウト)を経験した。
停電は“全部止まる”が本質だ。だからBCPは、発電設備の導入だけでは片手落ちになる。どこに、どれだけ、優先的に電気を回すか。運用設計が主役だ。
今回の取り組みでは、厳格な温度管理が必要な「麹室」への優先供給に言及している。酒造りの価値が失われるポイントを知った上で、電源を配置する。ここが実装のリアリティである。
脱炭素は“きれいな電気”の話に見えがちだが、地域産業にとっては“守りの電気”でもある。
あわせて読みたい記事

酒造りで発生するCO₂を活用し、植物を育てる「酒造り×農業」循環プロジェクトが始動。

電気も水も100%自給自足。気候変動時代のモバイルハウス、「ゼロインフラASOBOX」は買いか?

【建築デザインとエネルギーの両立】エネルギーをつくる屋根一体型太陽光「Roof–1」の狙いとは?